「サン・ジェルマン・デ・プレ」
パリに来たことのない人でも、この名前はどこかで耳にしたことがあるに違いない。
そこはシャンゼリゼやオペラ、マレとならび、パリの代名詞ともいえる地区。パリはセーヌ川の河口に向かって左側、つまり南側が「左岸」、反対は「右岸」と呼ばれるが、「パリ左岸」という憧れの響きとともに真っ先に思い浮かぶのはこの界隈の風景だ。

パリを知る方々には言うまでもないだろうが、サン・ジェルマン・デ・プレには芸術と文化、ファッションとグルメといったあらゆるパリの上質なエッセンスが詰まっている。
シンボルとなる「サン・ジェルマン・デ・プレ教会」にならんで、小説家や詩人、哲学者たちが集ったカフェ「レ・ドゥ・マゴ」「カフェ・ド・フロール」がある。さらにボナパルト通りに入れば「パリ国立高等美術学校」通称ボザールがあって、昔も今も、フランス国内をはじめ世界から集まった芸術家たちが街を行き交う。それを取り巻くように、古代から現代まで、ありとあらゆるアートや骨董を扱うギャラリーが集まり、さらにはインテリアショップや世界に冠たるモードのブランドショップ、老舗ショコラティエなどが点在する。
それほど大きくないエリアに、まさに宝石のような輝きが散りばめられた街、それがサン・ジェルマン・デ・プレだ。

バカンスシーズン真っ盛りの8月、この街の密かなアート探訪に出かけてみた。
名実ともにこの街のシンボルは「サン・ジェルマン・デ・プレ教会」。ここに最初の修道院と付属の教会が創設されたのは西暦543年というから、もう今から1500年近くも前になる。パリではもっとも古い教会だ。当時パリの教会区を治めたジェルマン司教が国王とともに創ったことから、のちに教会名となり、街もその名で呼ばれるようになったという。

とんがり屋根の鐘楼をはじめ、いま私たちが見ている教会の建物は11〜12世紀に再建されたもの。日本では平安時代の終わり頃にあたる。
まわりに見るべきものが多いせいか、この教会の中を見学する人があまりいないのは残念なことだ。というのも、少し前まではススで汚れ、冴えない内装だったのが、2015年に大規模な修復が始まり、主要部分の壁画や装飾がかつての輝きを取り戻してきた。
今年予定されていた修復の完了は2021年まで延びそうだが、すでにいまは見違えるような美しい教会内部を見ることができる。

フランスで教会といえば、うす暗いイメージ、または石灰岩や砂岩のさっぱりした白っぽい内部のイメージがある人も多いかもしれない。実は、もともとの教会はこのように鮮やかな色彩や金で美しく装飾され、天井は星空をイメージした青で彩られていることが多かった。それがフランスの場合には、のちの市民革命のときに削られたり、時間とともに退色、または汚れたままになって原形をとどめていないことも少なくない。

壁面に『旧約聖書』と『新約聖書』のさまざまなキリスト教の逸話を描いた19世紀の絵画も、いまは生き生きとそのストーリーを伝えてくれる。昔の人々がどんな思いでこれを見ていたのだろうかと、つい想像してしまう。
さて、教会を出ると横には小さな公園がある。その入口になにげなくおかれているのは、あのパブロ・ピカソによるブロンズ像『La Poésie 詩情』。台座には「ギヨーム・アポリネールへ」とフランスを代表する詩人の名が刻んであるが、顔はどうも女性のようだ。

これは1951年に、パリ市が目の前の道を「修道院通り」から「ギヨーム・アポリネール通り」と改名したあと、何かシンボルをと探しているところにピカソがこのブロンズ像の寄贈を申し出たらしい。胸像のモデルは、ピカソのかつてのミューズであり愛人であった写真家のドラ・マール。なぜアポリネールのオマージュにドラ・マールなのかよくわからないが、『詩情』と名づければなんとかつじつまが合うとピカソが思ったのかもしれない。
しかしこの像は1999年3月30日の夜に台座ごと忽然と姿を消す。警察が乗り出すが見つからず、パリ市もあきらめて複製を注文しようかという時に、50kmほど離れた森に打ち捨てられているのが見つかった。単なるいたずらだったのか、実は精巧な複製とすり替えられているのか。事件の真相は解明されないまま今に至る。

このギヨーム・アポリネール通りを歩いて行くと、静かな一角に小さな美術館がある。それがドラクロワ美術館だ。ウジェーヌ・ドラクロワは19世紀フランスを代表するロマン派の画家。もっとも有名な作品は、ルーブル美術館に所蔵されている『民衆を導く自由』(1830)。そう、トリコロール(三色旗)を掲げた自由を象徴する女性を中心にして、民衆たちが武器を手に、戦いに挑むさまを描いたあの大作の作者がドラクロワだ。
そのドラクロワが人生最後の住居とアトリエを構えたのが、サン・ジェルマン・デ・プレ地区の真ん中、ここフュルステンベルグ広場の建物だった。高級住宅街の一面も持つこのエリアを象徴するような思いがけないほどの静けさと、広場を覆い尽くすような木々の緑。ドラクロワ美術館はいま、ルーブル美術館に附属する国立の美術館として見学者を迎える。
美術館は、彼の作品やその他のアーティストの作品をふくめ現在約1,300点の絵画、デッサン、版画、手記、そしてオブジェなどをコレクションしている。自身の作品のほか、彼が影響を受けた画家、あるいは逆に彼へのオマージュを込めて作られた他の有名画家の作品も多い。

ドラクロワが制作に使った中庭横のアトリエには、いくつかの作品や彼が実際に使用したパレットなどが展示されている。なかでも目を惹くのは、先述した『民衆を率いる自由』の、ドラクロワ自身によるデッサン(素描)だ。

ルーブル美術館のほうは幅が約3m25cmもある巨大な作品だが、それを描くために彼は数多くの下絵で準備した。そのほとんどはドラクロワの手帖に鉛筆で記されているが、これは油絵で描かれた唯一のもの。女性の手の角度や旗の位置、登場人物や細かなディテールはまだだいぶ違っているが、この時点ですでに大事な構図は決まっていたことになる。
1857年12月、59歳のドラクロワがここに来たのは、彼が天井画の依頼を受けたサン・シュルピス教会に通うのに、オペラ座の北側にあった前のアトリエからはあまりに遠かったからだった。

このとき彼はすでに重い病に冒されていた。それでもなお教会の作画にこだわったのは、一人の人間の「遺言」としてこれを後世に残したかったからだという。この中庭の美しい眺めは、彼の心を穏やかにし、日記や手紙に度々その喜びを記した。
1861年にサン・シュルピス教会のチャペルの仕事を終えたあと、1863年8月13日、ウジェーヌ・ドラクロワはこの隠れ家のようなサン・ジェルマン・デ・プレの自宅で生涯を閉じた。
一時は、入れ替わった住人が車のガレージを作ろうとアトリエを解体する話が持ち上がったが、モーリス・ドゥニやポール・シニャックなど後世の画家らの動きもあり、危機をまぬがれた。静かな紆余曲折を経て国の手に渡ったのは、1954年のことだった。
いま数々の有数なアートギャラリーが立ち並ぶこの街の中で、偉大な画家の足跡を残したこの小さなドラクロワ美術館が残されていることがどれだけ意味のあることか。そして住む人々にもどれだけの豊かさを感じさせてくれることか・・・。 この中庭に佇んでいると、そうした文化に対する人の想いがゆっくりと伝わってくるようだ。

文・写真
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳などとして幅広く活動。


















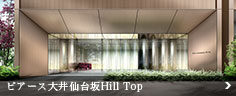






-7.png)
-4.png)

