ロックダウンがあけて、人々が街に戻ってきたのもつかの間。今度はバカンスシーズンになってパリがまた静かになってきた。ふだんなら世界から押し寄せる観光客も、今年はとても少ない。「いまがチャンス」とばかりに、地元のアートファンやバカンスでパリに来た家族などのあいだで、静かな美術館めぐりが人気だ。
オルセー美術館が6月23日に、ルーブル美術館が7月6日に再開したのをはじめ、市内の美術館や博物館が次々とその扉を開放し始めたパリ。気持ちのいい夏空のもと街を歩き、アートを楽しみ、ようやく店内に入れるようになったレストランやカフェで一息・・・。コロナの不安は少し残りつつも、めったにない「空いたパリ」の生活を謳歌しているようにみえる。

エッフェル塔からもほど近いアルマ=マルソー地区からイエナ地区にかけても、そんな静かなアート散歩にはもってこい。セーヌ川とエッフェル塔、岸辺に浮かぶ船とまわりの緑が絶妙なバランスで景色を彩る歩行者専用のドゥビリ橋は、パリを代表する絶景ポイント。まるで自分も絵の一部になるかのような景色に、ただ歩いているだけで幸せな気分になる。


この橋のたもとにあるのが、パリ市近代美術館。なにやら荘厳な宮殿のような建築は、1937年パリ万国博覧会の美術展示場として建てられたもの。ほぼ左右対称の左側はいま、現代アートの殿堂として知られるパレ・ド・トーキョー、そして右側がパリ市近代美術館だ。先ほどのドゥビリ橋も、そもそもはこのパリ万博のときにセーヌ川両岸に並んだパビリオン群をつなぐために作られたのが最初。世界中の文化が一堂に会した様子も、人々が行き来した情景も、パビリオンのない今はもう想像がつかない。

ところで、パリの「近代美術」と聞けば、まっさきに思いつくのはオルセー美術館だろう。あちらは印象派やその前後の時代を筆頭に、主に19世紀の絵画や彫刻の名作が並ぶ。一方こちらは、1905年頃に評判になったフォーヴィズム(野獣派)、あるいはキュビズムと呼ばれる潮流から、20世紀全般にわたる芸術家まで、約1万点の作品を所蔵する。

ピカソ、マティス、ルオー、ボナール、フジタ、ドロネー、ローランサンなど、パリがまさに「芸術の都」としての全盛期を迎えていた頃から、ヌーヴォー・レアリスム、フルクサスといった戦後の芸術運動の作家まで幅広い。その充実ぶりながら、パリ市の持ち物ということもあって常設展は無料で見ることができるのがフランスならでは。


自然光をふんだんに採り入れた壮大な空間は、さすがフランスの偉大さを見せようとした万博当時の意気込みを感じる。ときどき窓の外にエッフェル塔やセーヌ川を眺めながら、時代を追うようにアートの変遷を見ることができる。

今回の取材で、気になった作品があった。それは20世紀前半のシュルレアリスム芸術に大きな影響を与え、あのサルヴァドール・ダリも憧れたとされるイタリアの美術家ジョルジュ・デ・キリコの小さな彫刻《不安を与えるミューズたち》だ。
デ・キリコは、同じタイトルで絵画作品もいくつか残している。ギリシャ神話風の服をまとったミューズには、顔がない。絵画には他に描かれたオブジェから、この「顔がない」ことにさまざまな解釈を呼び起こすのだが、彫刻の場合にはその形に純粋に魅せられ、「不安」すら感じさせないから不思議だ。いろいろと語られる意味はあるが、もしかしたらデ・キリコはこのフォルムそのものを気に入っていただけなのかもしれない。そんな妄想さえ抱いてしまった。
アートの世界が多彩な方向に開きはじめた時代の、ありとあらゆる表現。肩肘張らずに思いのままに見ていけば、かならず自分の好きな作品に出会えるはずだ。

この美術館の正面入口の向かいには、パリ市立モード美術館「ガリエラ宮」がある。現在、内部はリニューアル中でこの秋オープン予定。今は前庭のみ公園として開放され、市民の憩いの場になっている。木々に包まれ、美しい建物と花々を眺めながらベンチでくつろいだり読書したりと、至福の時間がそこにある。
1894年完成のこの建物だが、パリ市の所有になったのにはちょっと間の抜けた逸話がある。建築主はイタリア生まれのガリエラ公爵夫人、マリア・ブリニョーレ=サーレ。彼女は自身の絵画・彫刻コレクションを保存し、一般に公開するために建物を計画し、国に寄贈することに決めた。当時の貴族らしい気前のよさである。

ところが、この寄贈の手続きをする公証人が、寄贈先に「国」と書くべきところを「パリ市」と書いてしまったのだった。気づいた時はすでに遅し。夫人はそれでも国への寄贈にこだわったが変更はできず、彼女は自分のコレクションをイタリアに送り、工事が終わっていない建物と残りの建設費をパリ市に譲り、「使い道は自由に」という妥協案で決着した。

なんとも歯切れの悪い結末だが、ともかくこの美しい建築はパリ市のものになった。のちに市はここをモードの美術館とし、現在は衣服、帽子、靴、バッグなど数万点ものコレクションを所有する。2017年からはスペイン・ビルバオ出身のファッションを中心にした美術史家、ミレン・アルサリュスが美術館のディレクターになった。
2020年秋のリニューアルオープンは、シャネルの創設者、ガブリエル・シャネルのフランス初となる回顧展。この華麗な舞台でどんな展示を見せてくれるのか、今から楽しみだ。

さて、パリ市近代美術館とこのガリエラ宮のあいだのウィルソン大統領通りを下っていくと、アルマ・マルソー地区。そこからさらにシャンゼリゼ大通りに向けて歩くと「シャンゼリゼ劇場」、世界中からセレブリティたちが集まるパラスホテル「プラザ・アテネ」があり、そこからはジョルジオ・アルマーニやクリスチャン・ディオール、ジバンシー、シャネルなどトップブランドが美しさを競うブティック街、モンテーニュ通りだ。

アートとファッション、新旧さまざまの建築、それを守り受け継いでいく人々と街の矜持。パリの中でももっともパリらしい街並みは、風景そのものが芸術品のように気品に満ちていた。
(文・写真)
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、キュレーター、コーディネーター、日仏通訳などとして幅広く活動。


















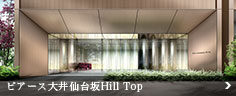






-7.png)
-4.png)

