みなさんこんにちは。我々弁護士がよく聞かれる、専門分野は何ですか?の質問。定番のようで、実は少し難しい質問でもあり、何でも駆け込み寺を目指す私もしばしば回答に数秒のタイムロスを生じさせてしまってます。もちろん分野に特化した弁護士も多数いて、特に刑事弁護や知的財産に関しては特化した事務所もよくあります。一方で、分野に括れなかったり、分野を跨いでいる事件も多いため、専門をうたわず活動する弁護士も多いのです。
そのため、何か困ったことがあったときには、専門の弁護士を探して相談しないといけないのでは…!と思わず、まずはアクセスできる弁護士に何でも話してみていただければと思っています。
さてそんな中でも、世の中に多く存在するご相談があります。誰でも直面しうる問題であり、私も常にご依頼を抱えている分野が、「相続」です。今回は「相続」について、今さら聞きにくいかもしれない第一歩のところからお話していきます。
1 相続とは何か
相続とは、端的にいうと、誰かが亡くなったときに、その人が所有していた全ての財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことです。(混同されがちですが、相続をして継いでいく人を”相続人”、亡くなった人、相続する人を”被相続人”といいます。)
財産、というとプラスのイメージを持つかもしれませんが、人にはマイナスの財産もあります。例えば、被相続人が借金をしていた場合には、相続人はその負債も相続するため、返済義務を負うことになるのです。
2 誰が相続するのか
原則として、誰が相続することになるかは、民法で定められています。この定められた相続人を、法定相続人といいます。
例えば、被相続人について、
①配偶者、子どもがいない場合 → 親や祖父母、亡くなっていれば兄弟姉妹
②配偶者または子どものみがいる場合 → 配偶者または子ども
③配偶者と子どもがいる場合 → 配偶者(1/2)、子ども(1/2)
④子どもはいなくて、配偶者と親が生きている場合 → 配偶者(2/3)、親(1/3)
⑤子どもはいなくて、配偶者と自分の兄弟姉妹が生きている場合 → 配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)
というように定められています。(括弧内は相続分)
3 遺言書が見つかったら
人が亡くなり、相続を考える際には、遺言書の有無が大きく影響します。遺言書は、皆さんご存知のように、被相続人が生前に、誰にどんな財産を残したいかを記したものです。法定相続人の誰かでも、それ以外の誰かに対してでも、自由に財産を残すことができます。遺言により財産を受け取ることになる人を、受遺者といいます。
では、先ほど記載した法定相続人と受遺者とは、どのような関係になるのでしょうか。これについては、民法の記載よりも、遺言書に記載された内容、本人の意思が優先されることになっています。つまり法定相続人がいる場合でも、遺言書に従った内容で受遺者が相続することになるのです。
実は、遺言書の作成にもルールがあるので、どんな記載の仕方であっても必ず遺言書に効力があるというわけではありません。ルールに従った遺言書だけが効力を有しますので、もし遺言書を残したいとお考えの方は、この点十分に注意してください。せっかく遺言書が見つかったのに、形式面の不備から本人の意思を貫けなかったという悲しいケースもよく見られます。自分の死後に、自分が財産を残したい相手に確実に届けるために、心配な方は弁護士に作成の相談をする、公正証書にする、といった対策を考えていただくといいかと思います。
4 遺言書は無敵?
では逆に、遺言書があった場合には、100%それに従うことになるのでしょうか? 被相続人がたまたま昔に書いていた遺言書が見つかったものの実は死亡直前にはその意思が変化していたと考えられる場合、また相続人内で遺言書にどうしても納得いかない場合、などもあるでしょう。そんなときは、遺言書記載の内容を修正できる、以下の方法があります。
- 受遺者、法定相続人の全員で話し合いをする
受遺者と法定相続人の全員で遺産分割に関する協議を行い、遺産をどのように分けるのかについて合意ができれば、遺言書に従わない相続をすることが可能になります。残された者達に支障のある遺言なのであれば、それに縛られずに済むようになっているということですね。ただし、皆さんのご想像の通り、なかなかこのケースは少ないかもしれません…
- 遺留分の請求をする
遺言があった場合でも、法定相続人には、遺産の一部である「遺留分」について相続できる権利が民法により定められています。そのため、受遺者に対し、自分の遺留分を引き渡してもらうよう請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。法定相続分よりは少なくなりますが、遺言書の内容に「待った」をかけられる制度です。なお、請求には期限があります。基本的には、①被相続人が死亡したこと、自らの遺留分を侵害するような遺贈等があったことを知った時から1年以内、または②被相続人の死亡から10年以内には、請求をしないといけない点はご注意ください。
5 相続をしたくないとき
そもそも相続は必ずしないといけないのでしょうか。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合等、諸事情から相続を拒否したいこともあります。そのような場合には、「相続放棄」や「限定承認」という手続きをとることができます。これらは、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から3か月以内に、裁判所に申し出る必要があります。
確実にマイナスが多い、または他の事情から相続をしたくない場合には、相続放棄により、プラスもマイナスも一切の財産を相続しないことができる手続きです。また、もし財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない…等の場合には、限定承認という手続きが適することもあります。財産を調査した結果、マイナスの財産が大きかった場合には、プラス財産の額の限りで返済するという制度です。
期限内にこれらを判断するためにも、相続が発生し、遺言書または法定相続により自分が相続することになる場合は、まずはプラスとマイナスの財産がどれだけあるのか確認することが重要になります。なお、3ヶ月では判断することが難しい場合には、熟慮期間延長申請も可能なことがありますので、その選択肢も検討しておくといいのではないでしょうか。
このように、相続といってもいくつものパターンがあり、ケースバイケースで必要な話し合いや手続きが大きく異なってきます。自分に関わる相続が生じた場合には、何をしなければならないのかを考えることが重要になりますので、参考にしていただければと思います。
この記事に関する質問や、記事で取り上げてほしい相談を受け付けております。
掲載記事については、モリモトSUMAUのInstagramにDMをお願いできたらと思います。

弁護士 菅原草子(スガワラソウコ)
仙台市出身。都内法律事務所所属。個人から企業まで分野を問わず相談をうける、駆け込み寺的存在を目指している。
大学院農学研究科で食品成分の研究をしていた異色の経歴をもち、企業の社外役員も務める。
趣味は、ビールと美味しいごはんと海外旅行。
instagram:@sooco_s328
記事で取り上げてほしい草子先生へのお悩みや法律の疑問を募集します
例えば最近ニュースでよく聞くこの法律について詳しく教えてほしい!など…
記事で取り上げてほしいことなら、小さなことでも大丈夫です。
SUMAUのインスタグラムからDMで気軽にメッセージをお送りください。
SUMAU公式インスタグラム@morimoto_sumau






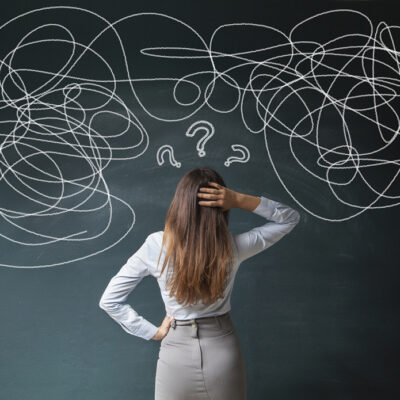











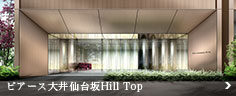






-7.png)
-4.png)

