いまパリは、秋色に染まっている。しかし美しい季節の移り変わりとは裏腹に、人々の暮らしには厳しさがつのる。
フランスは11月に入って、5月11日以来の再ロックダウンが始まってしまった。夏のバカンスのあと、新学年が始まる9月からはほとんどの活動が制限つきで再開されたが、それに合わせるようにコロナウィルスの感染も広がり、パリでは10月に夜間の外出禁止令もかけられたが間に合わなかった。
いつもなら、秋のパリは展覧会やアートフェアなど文化的なイベントが目白押し。しかし、世界屈指の現代アートフェア「FIAC(フィアック)」、そして写真のアートフェアである「パリ・フォト」という2大フェアが中止となり、ロックダウンにあわせて美術館もすべて閉鎖に。数多くのアートファンをがっかりさせた。

ただ幸いなことに、外出の制限は春よりも少し緩やかだ。日常の「必要品」とされる多くの店が開き、街頭のマルシェも許可されている。スマホのアプリでも作れる証明書を持ってさえいれば、1日1時間程度、家から1km圏の息抜き、運動は基本的に自由。週末ともなれば近所の公園にたくさんの人が集まって、ところどころは「密」になっている。

そして、目的地のない街歩きには、新しい発見がある。特にパリは、やはり建築の魅力が尽きない。市内では建物の高さがだいたい揃っているところが多いので、日本などに比べて風景には統一感があるように見えるのだが、ディテールではそれぞれかなり個性があることがわかる。長い街づくりの歴史の中で、その時代ごとに流行のスタイルや技術が反映され、積み重ねられ、モザイクのように入り組みながらパリの景色ができている。
よく知られているのが、アール・ヌーヴォーとアール・デコ。20世紀の前半を中心に流行した2つの装飾様式は、その名を聞いたことのある人も多いだろう。パリは1800年代の半ば頃から近代的な都市にするための大改造が行われて急激に発展するのだが、その頃からアートやデザインも進化と多様化を始めて、建築や新しい工業製品にもそれが次々と採り入れられるようになった。
その動きが一気に高まった時代に生まれたのがアール・ヌーヴォー(新しい芸術)だった。それまでの古典的なデザインにはなかった、花や植物のうねうねとした曲線、あるいは昆虫の形など有機的な装飾が特徴。ちょうど普及が進みはじめた鉄やガラスなどの新素材と合わせて提案されたものも多く、瞬く間にヨーロッパ中に広まった。1895年にパリの美術商サミュエル・ビングが「Maison de l’Art Nouveau アール・ヌーヴォーの館」というショールームをオープン、1900年のパリ万博で大きく採り上げられるなど、フランスでもいち早く「流行」。それを生かした建築が今も数多く残っている。

エクトール・ギマールは、その代表的な建築家。パリ16区に今もある集合住宅「カステル・ベランジェ」では、玄関の鉄製門扉をはじめバルコニーの手摺金物や装飾、タイルまで、その植物モチーフや曲線をふんだんに使っている。この建築は、パリ市が主宰した1898年の第1回「ファサード・コンクール」に入賞し、一躍ギマールは話題になった。

そして近代的な都市のデザインを意識しはじめたパリ市から、エクトール・ギマールが依頼を受けたのが、パリ万博にあわせて1900年に開通した地下鉄の駅入口デザインだ。当初は一般に公募されたらしいのだがあまり良いものが集まらず、この新しい様式で名を馳せていたギマールに白羽の矢があたり、指名発注となった。まるで地面から生えた植物のような柱が伸びて、つぼみか実か、あるいはトンボの眼のような赤いランプをつけている。これぞアール・ヌーヴォーの真骨頂といえるデザインだ。


パリのメトロは1913年までに10路線にも増えたのだが、その間167の駅入口がこのギマール・スタイルで設計されたという。今でもその多くが現役で使われているので、パリを訪れればかならずどこかで目にする機会があるはずだ。
パリ7区にある集合住宅「ラヴィロット館」も、アール・ヌーヴォー時代の名作。その名の通り、建築家のジュール・ラヴィロットの作品で、こちらも1901年のパリ市ファサード・コンクールに入賞している。



ご覧の通り、ギマールに輪をかけて個性的な装飾が特徴で、極めつけはやはりエントランス。植物はもちろん、孔雀、とかげなどさまざまなモチーフが入り交じったほとんど彫刻のような複雑な意匠に加え、建物のオーナーが陶作家だったこともあり、素材も陶器や木などが組み合わせてある。周囲のファサードと比べると、かなり異質な雰囲気が漂う。
実はこのやや過剰、官能的ともいえる装飾が、その後のアール・ヌーヴォーの命運を左右する。アール・ヌーヴォーは、家具、グラフィックアート、絵画、エミール・ガレに代表されるガラス製品や宝飾品などあらゆる分野に展開。ベルギー、オーストリアなどヨーロッパ中を席巻する。しかし、その複雑さがゆえに工業製品に向かず、コストも高く、さらに1914年からは第一次世界大戦も始まったこともあって、アール・ヌーヴォー的デザインは世紀末的、時に退廃的とも評されて世間から見放されることとなってしまった。
パリの建築も、こうした有機的な装飾への反動もあって、規律のある、幾何学的でシンプルな「アール・デコ」の時代へと移っていく。その表現の仕方は多様で、作り手によって、あるいは国によっても違ってくるのだが、前の時代との差は歴然だ。

パリの中心部にある「シャンゼリゼ劇場」は、アール・デコの初期の代表作。のちに「コンクリートの父」と呼ばれるようになる建築家オーギュスト・ペレなどによって設計された。「アール・デコ」という言葉は、フランス語の「Art Décoratif(アール・デコラティフ=装飾芸術)」が語源だが、これは1925年に開催されたパリ万博の正式名称「現代産業装飾芸術国際博覧会」からきている。すでに主流となりつつあった「アール・デコ」的なスタイルが、この万博によってあらためて言葉として定義され、新しい時代の到来を高らかに宣言した。

グラン・ブールヴァール地区にある「フォリー・ベルジェール劇場」、同じ地区の映画館「グラン・レックス」も、アール・デコ様式の代表的建築だ。シンメトリックで端正、そしてやや復古調の趣き、文字のタイポグラフィなどにもアール・ヌーヴォーの時代とは違った、当時の新しいスタイルを感じる。
フォリー・ベルジェール劇場を手がけたのは、フランスの建築家で装飾家、画家でもあったモーリス・ピコ。ファサードの中央にある金色のレリーフのモデルは、ロシア出身の女性ダンサー、リラ・ニコルスカだが、その身体は人間のナチュラルな線というより、デザイン化され幾何学的な曲線で描かれていて、まさにアール・デコの典型といえる。


アール・ヌーヴォーの有機的な曲線から、よりシンプルで幾何学的なデザインへ変化したアール・デコだったが、それでもなお「装飾的」であることに違いなかった。アール・デコの時代と並行するように、もっと装飾を削ぎ落として、機能を優先した形を求めたモダニズム建築の動きも始まり、やがて流行の座をそちらに譲ることになる。
こうした数十年、数百年単位の変遷を積み重ねてきたパリ。次に街を訪れるときには、ぜひ目的地のない散歩で、こうした建築の違いにも目を向けてみてはいかがだろうか。

(文・写真)
杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー
コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年より Art Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。


















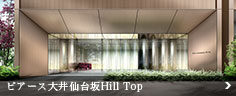






-1.png)
.png)

