人間が最初に「絵」を描き出したのはいつだろう?現代のように写真や動画もない時代、人の姿を残すには絵に描くしか方法がなかった。古代ローマの博物学者、大プリニウスが書いた『博物誌』に有名な逸話がある。ギリシャのコリントスという街で、ある陶器商の娘がいた。彼女には恋人がいたが、その彼が遠い場所に旅立ってしまうという。別れの夜、彼女はいとしさと別れの悲しみからランプの光がかたちどる彼の影を指でなぞった。それが絵画の起源になったというのだ。
そんな出来すぎたロマンティックな物語が、ほんとうに絵画の始まりだったかどうかは定かではないが、愛する人や家族、身近な人々が古代の画家たちの最初の「モデル」であっただろうことは想像に難くない。

まさにこの「ひとを描く」ことをテーマにした展覧会が、東京のアーティゾン美術館で開催されている。大プリニウスの物語のような古代ローマの時代、あるいはそのずっと前から、「ひとを描く」ことは作品制作では重要な要素のひとつだった。確かに美術史をひもとけば、ルネサンスの頃までは、絵画といえば教会が依頼するキリスト教の物語を描いた宗教画か、国王や貴族を描いた肖像画がほとんど。風景画やオブジェをメインに描くことなんて、ここ300年ほど前に始まったにすぎなかったりする。
展覧会は「ひとを描く」ことの初期に人々が込めた想いがわかる古代ギリシャの陶器の展示から始まる。そして時代を超えて、19世紀から20世紀にかけてマネやセザンヌ、マティスなどヨーロッパ近代画家が描いた人物画に焦点をあてた。ふたつの時代を通して、人を描こうとする「まなざし」の違い、その時代の背景などがわかって興味深い。そして85点におよぶ展示品のどれもが美術の歴史を語る逸品ばかりということで、名の知られた芸術家たちのスタイルもあらためて知ることができる。

まず登場するのは、古代ギリシャ陶器。そもそもなぜ陶器に人物が描かれているのか、現代の私たちの感覚からすると少し違和感があるかもしれない。古代ギリシャの陶器も最初の頃は幾何学模様がおおっていたらしい。それが紀元前8世紀中頃には人物や動物がまぎれるように現れるようになり、戦いや葬礼の場面が描かれ、やがて人物の文様が主役になっていったのだという。この時代は、紀元前8世紀半ば頃に吟遊詩人のホメーロスがギリシャ神話をまとめた叙事詩が誕生した頃に重なる。神々や自分たちの祖先の英雄伝などをつづったさまざまな物語を、繊細な絵付けの技術を磨いた絵師たちが描き、その陶器を酒の宴で使ったり、墓に納めたりといった大切な儀式に使用する。そんな古代ギリシャの成熟した文化が感じられる。

こちらは「黒像式技法」で作られた「ヘラクレスとケルベロス図」。力と勇気の象徴とされた英雄ヘラクレスが、伝令神ヘルメスと軍神アテナに導かれて冥府の番犬ゲルベロスを連れ出す場面。「黒像式技法」は紀元前7世紀末にアッティカ陶器に取り入れられたもので、それまでは単純な筆の線描きにとどまっていたのが、新しい手法を取り入れたことで、さまざまな場面を表現できるようになったのだという。赤褐色の素地の上に、まず図柄を影絵のように黒色で描いたあと、目鼻立ちや筋肉、衣類の線などを鋭い道具で削るようにして線を描く。こうすることでより繊細な人物の表現が可能になった。

今回の展覧会では、日本の近代画家、藤島武二と長谷川路可が古代ローマの人物画を模写した作品が初公開されている。藤島は1908年に、長谷川は1955年にそれぞれイタリアを訪れて、遺跡に見られるひとの描き方にインスピレーションを受けた。個人宅の建築でも人物画が描かれるようになった古代ローマ時代の変化。それを後世の日本人画家たちがどう捉えたのかを見つめてみたい。
そして時代はずっと先に進んで、19世紀から20世紀ヨーロッパの画家たちによる人物表現にフォーカスをあてる。この時代になると、画家たちはそれぞれにモデルを立て、あるいは自分自身をモデルにして絵を描いていく。そこに浮かび上がるのは、画家とモデルとの関係、あるいは自分を捉えるまなざし、そして人物を対象に何を描こうとするか、などといったさまざまな試み。古代ギリシャの時代とはまったく違うひとの描き方がそこにある。展示では、マネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、マティス、ピカソ、ジャコメッティといった近代アートの巨匠たちが描く「ひと」を、アーティゾン美術館の充実したコレクションから観ることができる。

たとえばこれ。そのタッチを見れば一目瞭然のルノワール。1876年に描かれたこの絵に描かれたのは、パリで出版業を営むジョルジュ・シャルパンティエの長女ジョルジェット。彼女は当時4歳。足を組んでおしゃまな感じで無邪気に振る舞う少女の姿や家の中の様子からは、19世紀パリの裕福な家庭の暮らしぶりがうかがえる。1876年といえば美術界に大きな衝撃を走らせた1874年の第1回印象派展からすぐあと。まだギリシャ・ローマ神話など「大きな物語」を描くことが良しとされた時代だが、ルノワールなど若手の画家たちはもう普通の人々を自由な色彩で描くことを躊躇しなかった。

そしてこちらに描かれたのは画家のヴラマンク。描いたのはその友人で、一緒にフォービスム(野獣派)という絵画の潮流を牽引した画家のドラン。左下にあるサインは、描いたほうではなく描かれたほうが書き込んだ「アンドレ・ドランによる私の肖像」の文字。芸術の新しいスタイルを共に生みだそうとした盟友関係にあった二人だったからこそ描けるこの親密さ。プロ並みの腕だったというバイオリンを流麗に奏でるヴラマンクの様子や音楽、仲間たちの笑い声までが聞こえてくるような作品だ。

そして打って変わってこちらはジャコメッティが描いた《矢内原》。ジャコメッティといえば、引き延ばされたような細い人物の彫刻が有名だが、同じように繊細な線で描く絵画の世界でも素晴らしい作品を多く残した。これは彼が1955年にパリで出逢った友人で日本人哲学者の矢内原伊作がモデル。ジャコメッティは人物をそのまま詳細に描くのではなく、モデルと自分自身との距離によって条件づけられた対象の見え方を絵に表そうとしたのだという。頭と胸の部分の無数の線とかき消されたような跡は、相手の存在を捉えようとする試行錯誤の表れなのかも知れない。

「ひとを描く」の究極形は、自画像だろう。セザンヌは、この《帽子をかぶった自画像》を始めとして、生涯で30点を超える自画像を描いた。彼はモデルを描くことがあまり得意ではなかった。画商のヴォラールの肖像画を描いたときには「りんごのように(ポーズを)持ちこたえてくれないと困る!」とイライラしながら言い放ったという逸話があるほど。だからこそ彼にとって自画像は、絵を探求するための恰好の題材だった。ほかにも自分をほとんど描かなかった貴重なマネの自画像も展示されているが、この作品にまつわる興味深い逸話はぜひ展覧会で見ていただきたい。
「ひとを描く」・・・一見、美術の世界ではよくあることに思われがちだが、そこには作品ごとに違うさまざまな想い、求めるものがある。一つ一つの作品から見える「ひと」を見つめる人間のまなざしについて、展覧会を通じて想いをめぐらせてみたい。
展覧会「ひとを描く」
会場:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館(東京・京橋)
会期:2025年2月9日(日)まで
開館時間:10:00〜18:00、毎週金曜日は20:00まで(入館は閉館の30分前まで)
休館日:月曜日(1月13日は開館)、12月28日〜1月3日、1月14日
詳しくは展覧会公式サイトへ
※記載情報は変更される場合があります。
※最新情報は展覧会公式サイトをご覧ください。



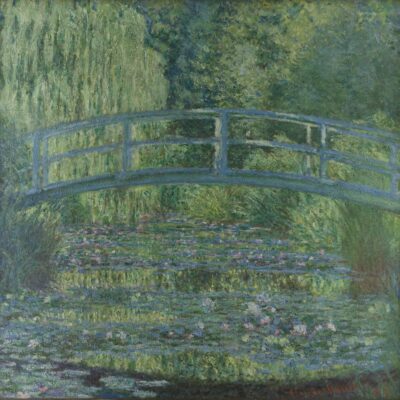




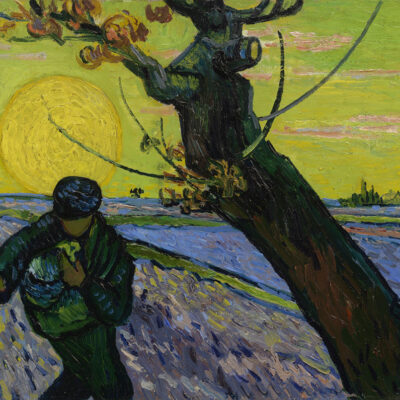







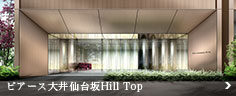






-7.png)
-4.png)

