誰もがスマートフォンという写真機をポケットやバッグに忍ばせて、気づくと一日に何枚ものシャッターを切っている時代。そんな私たちはふだん、写真に何を求め、何を写真におさめようとしているだろうか。
日常や旅の思い出。色鮮やかな季節の花やそこに煌めく太陽の光。心が動いた瞬間の記録・・・。しかしイタリアの写真家ルイジ・ギッリ(1943-1992)は、どうも私たちとはちょっと違う何かを見つめていたようだ。そこには、ぱっと見てわかるような驚きの瞬間や感動の瞬間が写っているわけではない。目の前にあるのに見過ごされそうな風景、そのなにげなく、はかない瞬間に現れた不思議な「磁力」のようなものの痕跡がそこに写しとられているように思える。

たとえば、この写真。タイル床に描かれているのはイタリアのカプリ島。おそらくこの女性が単にタイルの上を歩いただけなのだが、カプリ島を踏みつけるように見える瞬間を捉えたことで、風景の意味合いが変化する。踏みつける女性に何か思惑があるとか、その足が巨大な存在のように見えるとか。イタリア人らしい洋服や靴のセンスが、タイルの模様と見事に調和しているところにはルイジ・ギッリの遊び心も感じられ、それがまた私たちの想像や旅心を喚起する。これを撮影するまで、彼はどれだけの時間待ったのだろうなどと、いろいろな思いが頭をめぐる。
この夏、7月3日から9月28日まで、恵比寿ガーデンプレイスにある東京都写真美術館では、アジアでは初めてとなるルイジ・ギッリの個展が開催される。彼は1943年にイタリア北部のレッジョ・エミリア県スカンディアーノで生まれ、測量技師としてのキャリアを積んだのち、30歳をすぎてから本格的に写真を撮りはじめた。そして1992年にわずか49歳で亡くなるまで、約20年のあいだ独自の視点で風景を切り取ってきた。
ルイジ・ギッリが写真の世界に目覚めたのは、コンセプチュアル・アーティストたちとの出会いがきっかけだったという。写真イメージを作品に使用する現代美術のアーティストたちと制作を始めた彼は、出版界や報道写真などのいわゆる写真業界とは違う入口から写真を捉えたのだった。

彼にとって写真とは、現実世界の複製ではなく、撮影する人にフレーミングされ「見られた」視覚的断片によって風景を作り出すための手段だという。まるで錬金術師のように、丹念に世の中を見ながらシャッターを切るギッリにしか見えない瞬間。レンズ越しの世界は、看板やポスター、ガラスに写る影や白い壁、家のなかの椅子など、誰もがつい見過ごしてしまうものばかり。けれど、ギッリの眼と写真は、それを作品と呼べる風景に変えてしまう。

ありふれた公園のベンチについた一枚の白いスクリーン。そこに太陽の光が作った木々の影を、彼は見逃さなかった。その瞬間、この風景は不思議な力を持ち始め、作品の置かれた美術館のようになる。スクリーンは不意にひらかれた扉となって、私たちを別の世界へといざなうのだ。すぐ脇で何事もないかのように話し込む二人の男性の存在が、またおかしみを添える。

こちらは、石畳の上に立てられた小さな額縁。あなたはそこに何を想像するだろうか。TV画面のように突然何かが映し出されてドラマが始まる?いや、額縁のように見えるのは実は鏡。写っているのは自然の「空」だ。しかしそれが空だと知らない私たちは、その空っぽの面にさまざまな想像をしてしまう。これがおそらくギッリが追い求めた「見るとは何か」につながるのだろう。彼はただ現実を映しただけでなく、見る人の解釈や想像の余地をそこに残した。通り過ぎてしまいそうなシーンに、こうして新たな詩的な「風景」が作り出されるのだ。

「私は写真を作りたかったのではなく、写真であると同時に地図や設計図を作りたかったのです。」
これはルイジ・ギッリ自身が語った言葉だ。
彼が言う「地図」とは、世界を俯瞰する一般的な地図のようなものではない。実際にある足もとの風景を、彼が自分の眼で見て写真に収めながら「再定義」「再設計」することを言うのだろう。上の写真も、世界を把握するために撮影した写真の束こそが彼にとっての「地図」であり、それが背景の地図と重ねられることによって、その違いが強調されているとも言えそうだ。

こうしたルイジ・ギッリの写真は、今の私たちに、目の前にある風景を「見ることとは何か」を問いかけているように感じる。無数の写真が目の前を通り過ぎていくSNSの発達で、私たちはつい「写真映え」にこだわり、その「映え」る風景を複製したり、真似たりすることに歓びを感じてはいないだろうか。そうした「見つめ方」では、一瞬でわかる強い印象やわかりやすさに重きがおかれて、立ち止まって見る時間、ゆっくりした記憶、余白や沈黙は無視される。
ギッリの著作『写真講義』の中で、彼はこう語っている。「心のスイッチをONにすること、眼差しを活性化させること、現実の物や要素に別の意味を与えながらこれまで見えていなかったものやことを発見すること、これまでと違う方法で注視すること、こうしたことが重要なのです」(『写真講義』ルイジ・ギッリ著、萱野有美訳、みすず書房刊)
今回、東京都写真美術館の展覧会には、ルイジ・ギッリの初期の代表作から晩年の作品まで、約130点の作品、いわば彼の人生が記した「地図」が展示される。そのひとつひとつには、彼が世界をどう見たかが写っていると同時に、私たちに「どう見るか」を尋ねているように感じることだろう。写真を見る私たち観客の無数の視点がある限り、風景の見え方もまた無数だ。だからこそ展覧会のサブタイトルも「終わらない風景」なのだと思う。
ぜひ展覧会で、もう一度、「見る」とは何か、そしてこの世界の「見つめかた」について思いを馳せてみたい。
「総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ 終わらない風景」
会場:東京都写真美術館
会期:2025年7月3日(木)〜9月28日(日)
開館時間:10:00〜18:00(木・金曜日は20:00まで、ただし8/14(木)-9/26(金)までの木・金曜日は21:00まで)※入館は閉館30分前まで
休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館、翌平日は休館)
詳しくは美術館ウェブサイトへ
※記載情報は変更される場合があります。
※最新情報は公式サイトをご覧ください。
(文)杉浦岳史



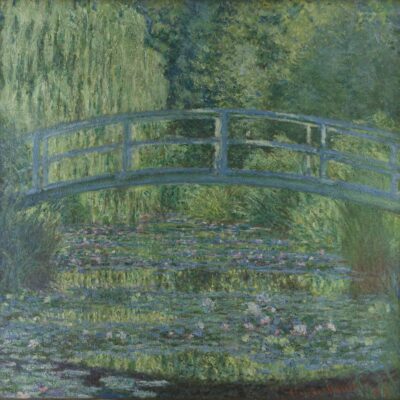



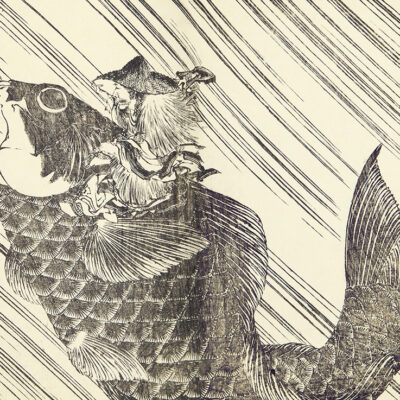
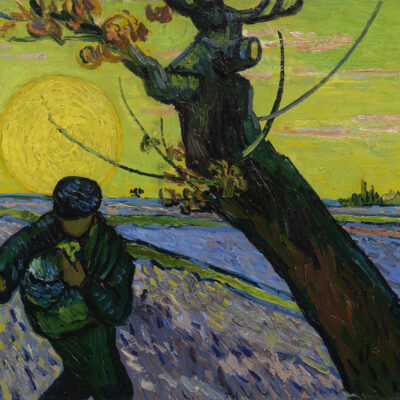






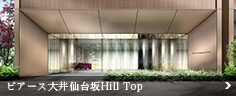






-5.png)
-1.png)

