世界中から数多くの訪問客を集めるスペイン・バルセロナのシンボル「サグラダ・ファミリア聖堂」。着工からすでに140年が経った今も建設が続き、長く「未完の聖堂」と言われていたこの建築の完成がそろそろ視野に収まってきていることをご存知だろうか。
これを生みだしたのは、建築家のアントニ・ガウディ。バルセロナがあるスペイン・カタルーニャ地方のレウスという街に生まれ、バルセロナ市内に点在するカサ・ビセンス、グエル公園、カサ・バッリョ、カサ・ミラ、そしてこのサグラダ・ファミリア聖堂などの有名建築を手がけてきた。これらは「アントニ・ガウディの作品群」として2005年にユネスコ世界文化遺産に登録されている。

ヨーロッパに数ある教会建築のイメージとは違う、美しく圧倒的なデザイン。空に手を伸ばそうとするかのような尖塔。どこか私たち人間の心に響き、呼応するような有機的な造形。しかも未知の文化に出逢ったかのような新鮮な驚きと感動・・・。そのユニークな存在は、ここを訪れた人を魅了してやまない。この独創的な建築は、ガウディがただ自由奔放に構想を描いたのではなく、西欧のゴシック建築や、スペインに根づいたイスラム建築、そしてカタルーニャ地方の歴史や自然風土を深く掘り下げることで至ったもの。さまざまなエッセンスが彼の中で混ざり合うことで、時代や様式を飛び越えるような革新的な表現にたどりついたと言われている。
東京国立近代美術館で開催中の「ガウディとサグラダ・ファミリア展」は、このガウディの建築思想と造形原理を「サグラダ・ファミリア聖堂」に焦点をあてて探り、読み解いていくものだ。ガウディの頭の中をのぞいてみるような展覧会と言ってもいい。図面だけではなく、膨大な数の模型を作ることで構想を練り上げていったガウディ独自の制作方法、さらには建築だけでなく彫刻も自分で手がけた彼の芸術的志向にも光をあてる。
あわせて100点を超える図面、模型、写真、資料、そしてNHK撮影による最新の高精細映像やドローン映像をまじえながら、ガウディの作品世界に迫っていく展覧会。私たちの好奇心だけでなく、創造性にもインスピレーションを与えてくれるに違いない。
ガウディの時代と彼の創造の源泉を探る

これはガウディが建築学校を卒業して間もない1878年の頃の写真。実は恥ずかしがり屋で写真嫌いでも知られ、きちんと顔が映った写真はこれをふくめ5枚しか確認されていないという。
そんなガウディの創造の源泉を知るには、まずは時代や彼の人生という背景を見ていく必要がある。彼が建築家を目指してバルセロナ建築学校で学んでいた19世紀の後半は、産業革命と都市の人口急増で、ヨーロッパの都市が大きな変貌を遂げていた時代。その代表ともいえるパリやロンドンを中心に「万国博覧会」が競うように開催されていたことでも知られる。
バルセロナは、スペインの中でも近代化が進んだ都市で、芸術の領域でも前衛的なムーブメントが花開いた。ガウディはその進歩的な街で建築家として活動を始め、ある有名な革手袋店の経営者から1878年パリ万博に出品するショーケースのデザインを依頼される。

1878年、名刺の裏、レウス市博物館
細身の枠でガラスを固定した軽やかでモダンなケースは、会場で評判となり、バルセロナの資産家アウゼビ・グエルの目に留まった。これがのちにガウディのパトロンとなったグエルとの関係を築くきっかけになった。
「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発する」
これはガウディ本人が語った言葉だ。彼は図書館に通い、ゴシック建築をはじめとした古今東西の建築をつぶさに研究するとともに、カタルーニャの遺産を発掘して地域に根ざしたアイデンティティを再発見しようとする組織にも参加した。また「自然は私の師だ」と語り、自然の観察によって造形の原理を引き出し、有機的なフォルムの建築や什器をデザイン。中には現場の敷地内にあった棕櫚の葉をかたどって鋳型を作り、門扉をデザインすることもあったという。こうした自然をもとにした装飾の究極の形が、のちにサグラダ・ファミリア聖堂に結実。ファサードにあたる「降誕の正面」には、植物や小動物をはじめとした生物の多様性が表現されている。

19世紀は地質学や考古学が発達し、洞窟や鍾乳洞が次々に発見されて洞窟観光がブームになる時代でもあった。ガウディもスペイン・マリョルカ島の鍾乳洞を訪れ、その自然の造形、古来から聖なる空間だった洞窟の象徴性にも関心を抱いていたという。また教会建築のデザインを構想するにあたり、ガウディは糸の両端を固定して下に垂らし、下向きの逆アーチを得る「逆さ吊り実験」をしていたことがよく知られている。「柱は木の幹、屋根は斜面と頂上をもつ山、ヴォールトはパラボラ(放物線)断面の洞窟」と語ったガウディ。彼はこのように自然から得たイメージに幾何学を応用することで、合理的な構造を兼ね備えた独自の造形言語を発展させたのだった。展覧会では、その構想に至る実験の様子や貴重な自筆のスケッチが来日し、彼の思考をたどることができる。
サグラダ・ファミリア聖堂の軌跡

サグラダ・ファミリア聖堂は当初、建築家フランシスコ・デ・パウラ・ビリャールによる計画案で構想が進んでいた。ガウディが二代目の建築家に就いたのは31歳になる1883年のこと。それから1926年に亡くなるまで彼はその設計と建設に心血を注いだ。
彼は膨大な数の模型を作り、それに修正を加えながら外観や内部構造を練り上げるという独自の方法で建設を進めていったという。展覧会では「森」のような内部空間、「降誕の正面」の建築造形の由来やガウディの彫像術、大空に映える「鐘塔頂華」という頂上の装飾にスポットを当てる。中でも、中世のゴシック建築と同じく聖堂内部を森に見立てて、樹木のように枝分かれした円柱が天井ヴォールトを支える様子は、巨大建築を見慣れた現代の私たちにさえ驚異的に映る。


そして聖堂の高く聳える12本の鐘塔も特徴的だ。キリストの十二使徒を表現したこの建築のシンボルともいえる塔にはガウディも力を入れ、先端の装飾は最終案まで20種類ものデザインを作ったという。多面体と球体を組み合わせた複雑な形で、頂点には十字架、その下には使徒の頭文字、側面には「Hosanna(神を讃えよ)」などの祈祷句が刻まれている。赤、黄、金に彩られた頂華はベネチア産タイルのモザイク。そこにはイスラム建築装飾の影響も感じられる。

そしてガウディは、サグラダ・ファミリア聖堂の「降誕の正面」を、キリストの到来と幼・青少年時代を表現する「石のバイブル」として構想し、聖書の物語を表す浮彫と彫像で全面を装飾した。展覧会では、スペイン内戦時の破壊を逃れた貴重なガウディ本人のオリジナル彫刻を紹介。その静謐な美しさに注目したい。

1898-1900年、サグラダ・ファミリア聖堂 © Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família
ガウディは1926年、路面電車に轢かれるという痛ましい事故が原因で73歳で死去する。その後、1936年に始まったスペイン内戦で聖堂の一部は破壊され、図面類は焼失、模型も破壊されて建設は中断を余儀なくされた。
「サグラダ・ファミリア聖堂」の正式名称は「聖家族贖罪教会」という。「贖罪(しょくざい)」とは金銭や物品を出すことで罪のつぐないをすることで、当初はこの聖堂の建設も信者の寄付による資金によって行われてきた。このため建設工事はゆっくりとしか進まなかったが、のちに拝観者が増えたことで資金が増加。近年ではコンピュータの導入で設計と建設の連動が進み、さらに工事のスピードが早まった。
そしてサグラダ・ファミリア聖堂といえば、1978年以来ここで彫刻家として建設に携わる日本人、外尾悦郎を忘れることはできない。彼はガウディが残したわずかな資料を頼りに、「降誕の正面」の彫刻群で中央の扉の上を飾る9体の天使像を制作した。今回の展覧会では、2000年に砂岩で制作された石像に置き換わるまで実際に「降誕の正面」に仮設置されていた貴重な石膏像が展示される。

ガウディの思い
「この聖堂を完成したいとは思いません。というのも、そうすることが良いとは思わないからです。このような作品は長い時代の産物であるべきで、長ければ長いほど良いのです。モニュメントの精神は常に堅持されるべきですが、しかし聖堂はその精神を受け継ぐ幾世代もの人々の意識次第で生きも死にもし、そうした幾世代の人々と共に生き、形を取っていくのです」
このアントニ・ガウディの言葉通り、サグラダ・ファミリア聖堂はまるで中世の教会建築のように時間をかけ、空に向かって伸びてきた。今年11月には4つの福音書作家の塔のうち、マタイとヨハネの塔が完成予定。聖堂中央の最も高い塔となるイエスの塔は、ガウディの没後100年となる2026年までの完成を予定している。
一度完成ということになっても、修復を続けながら次の世代への継承の旅はつづく。人々が永遠に手をかけつづけることの重要性さえもガウディの構想にプログラムされていたのだとすれば、これはもうあっぱれというほかない。

ガウディとサグラダ・ファミリア展
会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー(東京・竹橋)
会期:2023年9月10日(日)まで※会期中一部展示替えあり
休館日:月曜日(7月17日(月・祝)は開館)、7月18日(火)
開館時間:10:00〜17:00(金・土曜日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで
観覧料・チケット予約その他の情報は展覧会HPへ
※本展は滋賀・愛知へ巡回予定です。



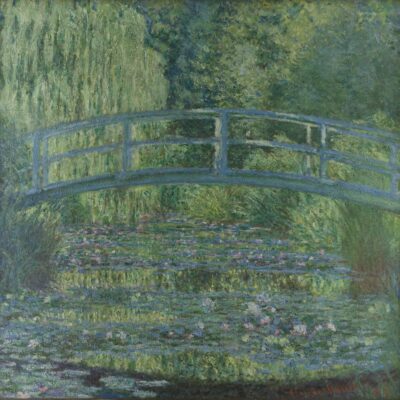



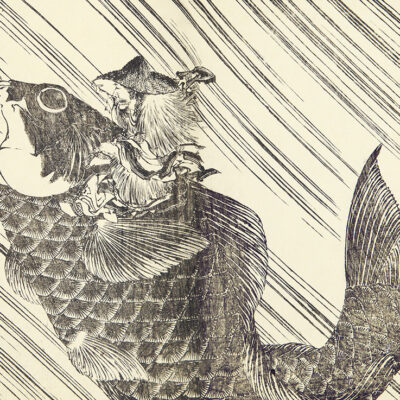
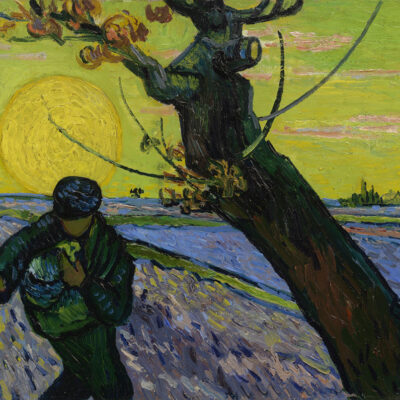







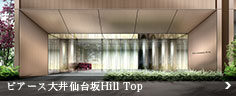






-7.png)
-4.png)

