「自分は誰か?」を見つける愉しみ
はじめは『セーラームーン』だったかもしれない。
思春期は『チャーリーズ・エンジェル』、少し前の記憶だと『Sex and the City』。
女性たちを魅了する映画には、条件がある。
「私、誰タイプだろう?」と占いや診断みたいに、複数の登場人物の中から自分を投影させられるキャラクターを見つける喜びがあること。
そこに答えを見いだしたって、見つけられなくたって、人生になんら変わりは無いのだけれど
“この中だと、自分は誰だろう?”
そんな問いかけは、誰のことも傷つけず、少女に戻ったように純粋に楽しくて仕方がない空想の1つだし、友人との会話のトピックに選べば”自分が誰かに判断されるおもしろさ”に触れられる。
私たちは、常に自分の分身みたいなものを探しているのかもしれない。
自分をあてはめて自己分析をしてみたり、自分以外の人からどう見られているか探ったり。
はたまた自分の心への効用として、決断の際はキャラクターの存在を思い出して背中を押されたり。
今回は、そんな楽しさを久しぶりに思い出させてくれた作品、魅力的な5人のエージェントが世界を救うミッションに挑むスパイ・アクション大作『355』について紹介したい。

圧倒的スケールのスパイ・アクション
あらすじと物語の魅力
CIA のメイス(ジェシカ・チャステイン)、ドイツ連邦情報局のマリー(ダイアン・クルーガー)、MI6のハディージャ(ルピタ・ニョンゴ)、コロンビアの諜報組織のグラシー(ペネロペ・クルス)、中国政府で働くリン・ミーシェン(ファン・ビンビン)ら5人の女性エージェントが集結。元は敵同士だった彼女たちは銃を向け合い対立する場面がありながらも、ハディージャの「私たちには共通の敵がいる」というひと言から、一致団結しミッションに挑んでいくことになります。
失敗すれば、第3次世界大戦がはじまるという緊迫した状況が続くなか、秘密兵器奪還に向けて国際テロ組織に立ち向かっていくチーム「355」。果たして世界の危機を救うことができるのか──?

輝かしい受賞歴とカリスマ性を兼ね備えた5人がパリ、ロンドン、モロッコ、上海といった風光明媚な世界の街並みを駆け巡る、しかもメインストリートのエリアだけじゃなくパリならば1番古いアーケード街のパサージュ・デ・パノラマ、ロンドンではビリンズゲートの巨大魚市場と、観光では訪れないような場所まで登場し、まさしく『ミッション:インポッシブル』『007』シリーズのような本格的なスパイ・アクションの女性版と名付けて相応しいほどの豪華な映画が誕生した。
各国のエージェントを演じる5人のヒロイン。
その魅力が5種5様で豊かなのはもちろんのこと、この映画の魅力はそれだけじゃない。
最初はそれぞれがライバル同士で敵とも言える立場であったにも関わらず、利害関係を越え世界秩序を守るために心を1つにして協力しあっていく。一見、相容れなさそうな女性たちの友情が結ばれていく過程、これがなによりもドラマチックだから、筆者は心惹かれた。
そんな女同士の心と心が重なっていくまでの過程の合間を、アクションやチェイス、個々の魅力を最大限に引き出すドレスシーンなどが盛大に味付けする。ゴージャスな展開とたくましい女たち。
本筋は彼女たちによる人間ドラマにあるからこそ、最初から最後までこちらも目で楽しむだけでなく、心で向き合うことができる。

この映画のアイデアを出したのはジェシカ・チャステイン。2016年にプロダクション会社フレクル・フィルムズを設立した彼女は今回、演じるだけでなくプロデューサーも務めている。
タイトルの『355』とは、かつて実際に存在していたと言われる女性エージェントのコードネームだ。
アメリカ独立戦争未解決のミステリーと言われ、ジョージ・ワシントン初代アメリカ合衆国大統領の諜報機関で中枢的な役割を担ったという。イギリス軍の動向についての機密情報をアメリカ将校に伝える役目を果たし、うまく機能したと言われている。
彼女のミッションの成果は記録され、いまでもその成功は忘れられていないが何百年経っても名前が未だに不明のままだ。そのことについてジェシカはこう語る。
「タイトルはとても重要です。 どの分野にも、舞台裏で人知れず根気強く働いてきた女性がいるのですから。 歴史の本を見ても、女性たちのストーリー、彼女たちが成し遂げたことが書かれていることは稀です。 『355』 というタイトルの映画は、認識されていない女性たちに対する敬意なのです。」

女性の活躍が難しかった時代があり、現在に至ってもなお、その問題は完全に解決されているとは言い難い。しかし、戦い続けてきてくれた先人がいたからこそ、幾分か道が歩きやすくなってきた”今”がある。
現在から過去へのラブレターのようなタイトルだと感じられる。

強い女は、如何にして強さを自分のものにしたのか
新たな場所での振る舞い方
私はこれまで強い女性像に幾度となく惹かれてきた。
「エリン・ブロコビッチ」「プラダを着た悪魔」「デンジャラス・ビューティー」「ワンダー・ウーマン」など、そのタイトルをあげだしたらキリがない。
その強さから生まれゆく自信というアクセサリーは、どんなジュエリーよりも表情を豊かに飾る。
憧れの要素に、近年”強さ”をかねそなえることはヒロインたちに欠かせない。

でも、そんな強靭なメンタルをもつ女は初めから”強かった”のだろうか?
実はそうではなく強い女は”強くあろうしている女”だったことを教えてくれるから、この映画は心強い。誰にだって変化のチャンスがあることを明示してくれる。
映画の中で飛躍的に成長を遂げるのが、ペネロペ・クルス演じるグラシー。
彼女はコロンビアの諜報局に送られたものの、普段の仕事は諜報員の心のケアをするドクターだ。冒険をするキャラクターではないし、銃や爆弾にだって、当然慣れていない。
エージェントモノと聞くと現実離れしたキャラによる娯楽的エンタメを想像してしまうが、そこの隙間を埋めてくれる彼女の存在があるので、彼女が接着剤の一部となり一般人の私達も作品世界にいっそう入り込むことができる。
グラシーの怯えていた陰りがちな瞳に、決意が宿りだす後半、その変化はドラマチック!
男性を誘惑するシーンでは微笑みを浮かべながらも、瞳に力を入れたと思えば、ふっと抜いて、目線ひとつの威力で人間が堕ちる。さすが情熱の国スペイン出身のペネロペ。彼女の瞳に意志が宿る瞬間は印象的で、麗しい。同性でもハッとしてしまう名シーンだ。

さて、話を戻そう。
強い女たちは初めからそうだったのではなく、おそらく強くあろうとした女なのではないだろうか。ちょっぴり荒療治かもしれないけれど、ときには徹底的に知らない環境の混沌に身を委ねるのもいいかもしれない。初めから強くなくたっていい。むしろ、”強くあるための決断”こそがその人を成長させることだっておおいにあることを映画は教えてくれる。
この世におそらく、弱い女なんていない。私たちは皆、平等に強くなれる。
この映画のくれたそんなメッセージに、やっぱり私は励まされるのだ。
(映画ソムリエ 東紗友美)

『355』
2月4日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー
配給:キノフィルムズ
©2020 UNIVERSAL STUDIOS. ©355 Film Rights, LLC 2021 All rights reserved.
監督:サイモン・キンバーグ
出演:ジェシカ・チャステイン ペネロペ・クルス ファン・ビンビン
ダイアン・クルーガー ルピタ・ニョンゴ with エドガー・ラミレス and セバスチャン・スタン-

映画ソムリエ東紗友美(ひがし・さゆみ)
1986年6月1日生まれ。2013年3月に4年間在籍した広告代理店を退職し、映画ソムリエとして活動。レギュラー番組にラジオ日本『モーニングクリップ』メインMC、映画専門チャンネル ザ・シネマ『プラチナシネマトーク』MC解説者など。
HP:http://higashisayumi.net/
Instagram:@higashisayumi
Blog:http://ameblo.jp/higashi-sayumi/





-400x400.jpg)












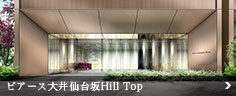






-7.png)
-4.png)

