女の子として産まれたにも関わらずピンク色が全く似合わず、幼少期の私は青い服ばかり着ていたという。その頃の影響だろうか、今も生まれてから日の浅い赤ちゃんが着ていそうな淡い水色の洋服や小物を見ると、つい飛びついてしまう。
ちょうど5年ほど前のこと、コロナ禍で外出がままならない時期にネットショッピングにはまってしまった。店頭での場合はあまり考えずに購入するのだが、インターネットでの場合はじっくり考えて(なんなら悩んでいる間に売り切れてしまって後悔することも)比較して買うことができるので、無駄がない。あるとき、バリエーションを増やそうと淡い青色の帯締めを調べ始めたのだが、この「比較」が問題で、多分店頭だったら最初に目に止まったものを買うのだろうけれど、画面上に一斉に青系統が並ぶともはや選べない。青と言っても、青みが強い浅葱色と比べると水色はちょっと緑がかって見えたりして、似ているのに少しの違いでどれも本当に素敵なのだ。緑色の信号を「青信号」と呼んだり、古九谷の「青手」が緑色の発色だったり、緑の野菜を「青菜」と言うことからも、青と緑色の色彩の曖昧さにはかねてから興味があった。そもそも青磁だって青い磁器でありながら、明時代のものなんて明らかに緑っぽい。青と緑の関係について調べれば、古く日本では赤・青・黒・白という4色しか呼び名がなく、緑は青色の中に含まれていたのだそうだ。



今日はまさにそんな青とも緑とも呼べそうな色彩が現れている青磁をご紹介したい。普段は料理から器を考えることが多いのだが、今回はこの季節だからこそ使いたい器を、と思って選んだ。晴れた青空と、大地が生命力を増すような新緑の季節が合わさるとこんな色になるのではないだろうか。青の和名で言うならば「水浅葱」、緑の和名で言うならば「千草色」。
13世紀頃(南宋時代)、今の中国浙江省の龍泉窯で作られた焼き物で、白味の胎土にたっぷりかかった粉青色釉と洗練された形が特徴の、上手の青磁は「砧青磁(きぬたせいじ)」と呼ばれている。口の部分がシャープであると同時に、輪花形なので華やかで優しい雰囲気もある。シンプルで、非の打ちどころのない美しいものだと思う。一方で、この焼き物を砧青磁と呼ぶようになった理由を知れば、その意外さに驚くかも知れない。かつて桃山時代の茶人 千利休が所有していたとされる「青磁鯱耳(しゃちみみ)花入」の胴の部分に大きなひび割れが入り、楔で止められているものがある。このひびが布を打つ砧の‘響き’にかけられたとか、また同じタイプの有名な花入「千声」「万声」の形が砧を打つ槌(つち)に似ているからとかで、そう呼ばれるようになったと言われる。
今回の料理は麻婆茄子だ。麻婆茄子は、麻婆豆腐から派生して日本で誕生したもので、本場では食べることができない。1980年代に丸美屋や味の素が、合わせ調味料を発売したことで広まった。日本人の味覚にすんなり馴染み、今日では和製中華料理として食卓を豊かにしてくれている。ところで麻婆とは一体なんなのだろうか。これは文字通り麻(痘痕=天然痘の後遺症として顔の皮膚にできる窪み)のある婆(老婦人)の作った豆腐料理が評判だったことに由来するらしい。料理の名前になってしまうなんて、その女性の料理はどれだけ美味しかったのだろうか!
麻婆茄子

―材料(2人分)
- ネギ(白い部分) 2分の1本
- 生姜 15g
- にんにく 10g
- 長ナス 2本(280g)
- 豚挽肉 180~200g
- 塩 6つまみ(3g)
- 片栗粉 大さじ3分の2
<合わせ調味料>
- 鶏ガラスープ 200ml ※鶏ガラスープの作り方は、海老とアスパラのチーズリゾットのレシピ工程①を参照
- 豆板醤 小さじ1
- 甜麺醤 大さじ1
- 砂糖 3g
- 醤油 3g
- 中国醤油(あれば) 1g
<お好みで>
- ラー油
- フォアジャオ
- 木の芽

1、下準備をする。ネギ・生姜・にんにくをみじん切りにしておく。

2、長ナスを乱切りして、塩水に5分ほどつけてアクを抜く。

3、鶏がらスープ・豆板醤・甜麺醤・砂糖・醤油・あれば中国醤油を合わせておく。

4、長ナスの水気をしっかりと切って、フライパンに多めの米油(分量外)をひいて、できるだけ短時間でしっかりと絡ませながら火を通す。火が通ったら、一度取り出す。

5、同じフライパンで、豚挽肉を炒め、色が変わったら、1のネギ・生姜・にんにくのみじん切りを加えて、さっと加熱し、さらに4の長ナスも戻し入れる。

6、ここへ3の合わせ調味料を加えてぐつぐつとさせたら、同量の水分で溶いた片栗粉を混ぜ入れながらとろみをつける。
7、器に盛ったら、好みでラー油・フォアジャオ・木の芽を乗せる。

今回はフライパン1つで作ることを想定したレシピとしたが、手間が気にならない方は長ナスを素揚げして使うことをおすすめする。この場合はあく抜きは不要、仕上がりの口当たりと長ナスの濃い紫色をより楽しむことができるだろう。

料理家 千 麻子
学習院大学文学部哲学科および経済学部経営学科を卒業し、史料館に勤めた。また美味しいもの好きが高じて美食の街、リヨンのポールボキューズ料理学校をはじめ、国内外問わず料理を学び、フランスではミシュラン3つ星のレストランの厨房でも研鑽を積む。
Instagram:@asako_sen















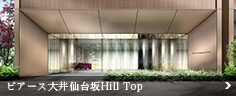






-7.png)
-4.png)

