子供が生まれてはや三ヶ月。ということで、お食い初めの準備にとりかかる昨今、この行事に欠かせない食材といえば鯛である。これまで祝いの席では当たり前のように鯛が出てきていたが、今回初めてなぜ珍重されてきたのかを知ることとなった。
鯛の身は白く、表面は赤く、あるがままの姿で紅白であり、魚の中でもとりわけ寿命が長く、バランスの整った形で味も良い。さらに「めでたい」という語呂の良さも手伝っている。平安時代の延喜式には朝廷への貢物として各地から鯛が納められたという記述が残り、古くから大切にされてきたことがわかる。また、神様のお食事として上がる神饌(しんせん)になることも多い。嫁ぎ先の京都の家では正月に、塩焼きにした尾頭付きの鯛の体にごまめを差し込んだものが居間に置かれていた。三日間は手をつけることが許されないので「睨み鯛」と呼ばれているが、これは三が日が明けると、お下がりとして初めていただくことができるものであった。このようなありがたい謂れの魚は、特に慶事の席では身に刃物を入れることなく尾頭付きでというのがお約束のようだ。
今回は鯛を使った昆布締めをご紹介する。昆布締めとは富山県の郷土料理で、昆布に食材を挟んだだけといういたってシンプルな調理方法である。何かで材料を挟んだだけであれば、私の馴染みあるフランス料理では仕込みに該当し、あくまでも一皿を構成するパーツにすぎないという感覚がある。しかし和食であれば、これほどシンプルなものが立派な主役の一皿となる。この違いは、和食に欠かせない昆布が鍵を握っている。昆布は単に海から引き上げられただけではなく、天日干しされ、さらに蔵で熟成されて私たちの手元にやってくる。うま味成分のグルタミン酸に加え、この工程によって昆布に含まれる栄養が甘み成分として現れるのだ。乾燥した昆布で挟むことで、水分を素早く吸収するので食材の日持ちがするようになること、そして昆布のうま味が移ることが利点であるが、これは乾燥昆布になるまでの過程で得られる効果であると言えよう。挟んで、あとはいただくだけという昆布締めは、実はそこに至るまでに長くの時間がかかっている。昆布締めの奥行きのある味は、一目ではわかりにくいおかげの賜物なのである。


今回の器は今から350年ほど前に中国で雑器として作られた古染付だ。見込みには蓮の花、葉、実などが結かれた束蓮文(そくれんもん)が描かれており、縁には椿と卍(まんじ)崩しがまるで額縁のように表されている。蓮は字の中に「連」があるように、物事が連続するという吉祥を意味している。日本では仏事のイメージが強い蓮も、中国ではおめでたい象徴なのだ。古染付は和洋中問わず、どんな料理も様になる使いやすい器なので1枚あると重宝するだろう。
【鯛の昆布締め】

材料(2人分)
・鯛(刺身用) 1冊
・昆布 適宜
・塩 適宜
・醤油 10g
・ゼラチン 1.5g
・酢橘 2分の1個
・芽ネギ 適宜
・花穂紫蘇 適宜

① 醤油酢橘ジュレを作る。ゼラチンを冷たい水につけてふやかして、水を切っておく。醤油10gと水40gを沸かして、ゼラチンを加えて混ぜたら、器に移して冷蔵庫に15分入れる。固まる前に酢橘を絞って、混ぜたら再び冷蔵庫で冷やす。

② 鯛を切る。包丁をねかせて刃元から刃先にかけて手前に引くような感覚で1度で切る。できるだけ前後に動かさないように心がけると良い。



③ 昆布締めを作る。濡れ布巾などで昆布の表面をさっと拭いておく。昆布に塩をふって、その上に鯛が重ならないように並べる。刺身の上からも塩をふって、昆布を重ねる。これをラップで包み、冷蔵庫で3時間休ませる。
※長時間つけすぎると昆布臭くなったり、水分が抜けてキシキシした食感になるので注意する。すぐに食べない場合は、時間が来たら昆布から取り出しておく。

④ 鯛を並べる。セルクルがない場合はランダムに刺身を広げても良い。上からスプーンで丸くしたジュレ、芽ネギ、花穂紫蘇を散らす。ジュレは、フォークでかき混ぜてクラッシュした状態で使っても。

昆布締めには塩味が付いているが、酢橘醤油のジュレと芽ネギ、花穂紫蘇と合わせることで華やかでありながらも、さっぱりといただける。
(撮影・古本麻由未)

料理家 千 麻子
学習院大学で美術史と経営学を専攻し、博物館に勤務。美味しいもの好きが高じてフランス随一の美食の街、リヨンのInstitut Paul Bocuseで料理を学び、ランスのレストランL’assiette champenoise(ミシュラン三つ星)の厨房で研鑽を積む。
Instagram: https://www.instagram.com/asako_sen/















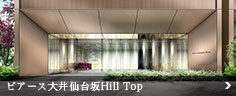






-7.png)
-4.png)

