鮭は母川回帰という、他には見られない習性を持つ特殊な魚だ。白身魚なのに体が赤く、海水にも淡水にも適応できるところが面白い。川で生まれて、その後数年を海で過ごし、匂いを頼りに元の川に傷だらけになりながら戻り、卵を産んで一生を終える。縄文の頃から鮭を食べていた北海道ではそういう性質が神秘的に映ったのだろうか、鮭を神の魚とも呼んだ。
ところで、いつから我々の祖先が、鮭の卵を食べるようになったのかは定かでない。お腹にぎっしりと卵が詰まっているのを見て、きっと驚いただろう。そして海水にさらしたり、手で引っ張ったり、どうしたら美味しく食べられるのか試行錯誤した人たちがいたかもしれない。
今のような塩気を帯びた食べ方はロシアから大正時代に入ってきた。チョウザメの卵の塩漬け、いわゆるキャビアの食べ方を参考にしたのが始まりだった。呼び名からもそれは明らかで、いくらの語源はロシア語で「小さくて粒々したもの」を指す。
鮭の体の中にはいくらがパラパラと入っていると思われるかもしれないが、それは違う。卵は膜につながり、守られるような形で存在している。そしていざ産卵を迎えると、膜から自然に一粒一粒と剥がれて川底に産み落とされる。ところが、私たちが産卵前に捕獲し取り出してしまうので、目にするのは膜に入った、筋子という状態だ。これを無理やり剥がさねばならないのだから、お湯を使い、ラケットに擦り付け、四苦八苦するのも当然のことである。とはいえ、この作業をすることで、生まれるはずだった命に感謝して一粒も無駄にすることなく大切にいただきたいという気持ちが生まれることも、また一つの事実である。
産卵直前の卵であるいくらは栄養の宝庫で、特にEPAやDHAの含有量は青魚よりも多い。血液がサラサラに、そして記憶力まで向上が望めるならばいただかないほかない。自分でいくらを作ることのメリットは、何よりも好みの味にできることだ。食欲の秋には、炊きたてのごはんと頬張りたい。
いくらごはん

―材料
・鮭の生筋子 2分の1腹
・塩 15g
・出汁(水でも可) 35 ml
・醤油 20 ml
・日本酒 60ml
・みりん 20 ml
・三つ葉 適宜
・炊いた米 適宜

①漬け汁を作る。日本酒とみりんを鍋に入れてトロッとした質感になるまで煮る。するとはじめの3分の1くらいの量になる。
②出汁、醤油と①を合わせる。使っている調味料の銘柄によって味が大きく異なるので、必ず味見をして好みに調整する。 あとから醤油を足して濃くすることはできるので、少し薄いかなと感じるくらいが良い。


③生筋子を広げて、泡立て器をあてて、ほぐすように動かす。

④分量外の水500mlに塩15gをいれて混ぜておく。ここにいくらを入れて、膜などの不純物を手で丁寧に取る。

⑤お米を研ぐ要領で、上澄みの水と白い膜を流し、新しい真水を加えて再度掃除する。くるくる手で混ぜると白い膜が浮かぶので、これを流す。同じことを3〜5回ほど繰り返すと、大体きれいになる。

⑥ザルにあげる。気になる汚れがあれば、手で取る。最初は全体的に白っぽくなっているが、数分で元の色に戻る。

⑦容器にいくらを入れて、②の漬け汁をいくらがひたひたになるように注ぐ。1日冷蔵庫で休ませてからが食べ頃。

⑧炊いた米に、三つ葉といくらの醤油漬けをたっぷりのせる。好みで海苔や柑橘の皮を削っても良い。


今回ご紹介するのは伊賀の岸野寛さんの灰釉飯碗(かいゆうめしわん)。薄くて軽やか、ご飯だけでなくお茶も映える茶碗で、日々の食卓に欠かせない。何を盛っても華やかになる万能な器の一つ。
料理家 千 麻子

学習院大学で美術史と経営学を専攻し、博物館に勤務。美味しいもの好きが高じてフランス随一の美食の街、リヨンのInstitut
Paul Bocuseで料理を学び、ランスのレストランL’assiette
champenoise(ミシュラン三つ星)の厨房で研鑽を積む。旅先で出会い、心に残った食べものを再現することが日々の愉しみ。
Instagram: https://www.instagram.com/asako_sen/















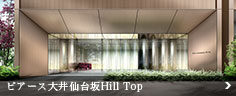






-7.png)
-4.png)

