変化が著しい時代の反動なのか、いま人々の間で「民藝(みんげい)」が注目されている。
そもそも「民藝」とは何だろう?これは「民衆的工芸」の略語で、1925年つまり今から100年近く前に生まれた造語。「芸術」ではなく、あくまで「工芸」であるところがポイントだ。一般的に「芸術」といえば、芸術家が生みだした特定の作品やその活動のことで、「工芸」は、土地に根ざし技術を習得した職人が人々の実用のために作りだすもの。古くからずっと庶民のあいだで当たり前のように使われてきた工芸、つまり日常の生活道具の中に、実は美が潜んでいるんじゃないか、と光を当てそれらを「民藝」と定義。その美的感覚や価値を再発見、新たな工芸に活かすことで、暮らしや社会を美的に変えていこうとした試みを「民藝運動」と呼ぶ。
今でこそ、こうした暮らしにまつわるモノづくり、プロダクトデザインなどは高く評価され、生活に採り入れることも当たり前のようになっているが、つい100年ほど前まではこうした「美」が表舞台で取り上げられることはなかった。
この「民藝」に注目し、その立役者の一人だった柳宗悦(やなぎむねよし)の没後60年を記念して開催されているのが、東京国立近代美術館の柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年」だ。

展覧会の第1章は、この「民藝」の運動がはじまる前夜まで話がさかのぼる。柳宗悦は結婚後に千葉県の我孫子に居を構えるのだが、そこに彼も参加した文芸雑誌『白樺』のメンバーである志賀直哉、武者小路実篤など錚々たる文人たちも移り住んだ。彼の生涯の友人となる英国人バーナード・リーチも窯を築くなど、柳自身が「コロニー」と呼ぶような芸術家村を育んでいたという。
それは1910年代の初め頃。遠くヨーロッパでは芸術の世界でモダニズムの大きな変化が起きていて、雑誌『白樺』はそれをいち早く紹介し、作品を蒐集したりもしていた。世界とつながりを持とうとした彼らは、フランスの彫刻家ロダンとの交流を試み、手紙とあわせ当時フランスで人気になっていた日本の浮世絵を送ったのだという。すると驚いたことにロダン側から三体の彫刻が返礼として届き、『白樺』メンバーを沸かせた。
展覧会には1911年にプレゼントされたこの彫刻も展示されている。「民藝」の展覧会にロダンとは不思議だが、実はこのロダンの彫刻こそが民藝運動誕生のひとつのきっかけになったのだ。
柳宗悦の書斎にやってきたこのロダン作品を、どうしても見たいと我孫子にやってきたのが、彫刻家を志していた浅川伯教。書斎訪問のお土産に、と彼が持参したのが今回ロダンと一緒に展示されている朝鮮の壺だった。

柳宗悦は、この壺の美しさに感銘を受け、無名の工芸品が持つ美に開眼した。その後、彼はたびたび朝鮮を訪れるようになり、陶磁器などの工芸品を蒐集。陶芸家の濱田庄司、河井寬次郎らとも出会い、意気投合する中で、次第に「民藝」という概念が培われることになっていく。
蒐集した朝鮮の工芸を一堂に集め、土地の人々に根ざした朝鮮民族美術館が1924年に実現。この成功に力を得て、1926年にはこの柳宗悦、濱田庄司、河井寬次郞に陶芸家の富本憲吉が加わり、4人による「日本民藝美術館設立趣意書」が発表され、公に「民藝」の構想を問うことになった。
展覧会の第2章は、鉄道を中心に交通網が発達する時代のなかで、柳たちが「旅」を通じて各地の民藝を発掘、蒐集していく様子を追っている。柳宗悦が調査・研究に力を入れた江戸時代の「木喰(もくじき)仏」との出会いもそのひとつ。彼は日本国中を巡って、各地に独特の仏像を残していた江戸時代の木喰上人の足跡を追った。

彼らの関心はヨーロッパの工芸運動にも向かっていた。1929年には柳と濱田が欧米旅行へ。各国で見たグローバルな工芸とその保存復興の気運、モダン・デザインの潮流なども参考にしながら、日本各地に眠る民藝を発見していった。


1920年代後半から30年代にかけて、民藝運動はさらに深まりを見せていく。ちょうど日本の急激な近代化がさまざまな矛盾をはらんだ時期で、発展した「都市」に対する「郷土」という考え方が生まれ、その地方での伝統的な生活の文化を再評価する動きが活発になった。
デザインなどメディアを駆使して「編集」する新しさ
実は「民藝運動」で注目すべきなのは、民藝そのものの美もさることながら、それを紹介するにあたって、デザインや編集の力が発揮されたという点だ。宗教哲学者、文筆家でありながら、絵心も持っていたという柳宗悦は、蒐集物をスケッチし、書体(フォント)を作り、写真やモチーフをトリミングして・・・と、デザインや編集の作業に腕をふるった。

これは1931年に民藝運動の機関誌として創刊された雑誌『工藝』。織物や漆絵を使ったその表紙やケースのデザインからして当時は斬新で、中の紙に各地の手漉き和紙を用いるなど、これ自体がまるで工芸品のようだ。
また下の写真にある武家の革羽織のように、ただ単にモノを紹介するだけでなく、民藝の一番良い部分の「美」を抽出してトリミングし、そのエッセンスを伝えようとしたことがわかる品もある。

こうした「美」のエッセンスを応用して、民藝をリニューアルする、あるいは新しい民藝を生みだす動きも始まっていた。柳の民藝運動に共感して活動を続けていた医師の吉田璋也は、1930年に郷里の鳥取に帰郷。新作民藝というスタイルで制作をスタート。江戸末期から続く牛ノ戸窯で、新しい生活にふさわしい日常の食器の生産を試みた。元々は褐色と黒の釉薬を掛け分けていたものを、写真のように銅緑釉と黒釉にアレンジ。柳宗悦も絶賛したといわれる。

吉田璋也はさらに、英国のホームスパンの毛糸のネクタイを手本にして、ニニグリ糸と呼ばれる、いわば不良品の繭で紡いだ糸を使って新しいデザインの《ににぐりネクタイ》を考案。農家の女性たちの副業として生産して人気商品になった。吉田は、こうした各地の新作民藝を販売する「たくみ工藝店」、今でいうセレクトショップも設立し、鳥取を拠点に民藝のプロデュース、流通も手がけていく。

1934年には、ここまで見てきた民藝運動の振興を主な目的とする「日本民藝協会」が発足し、1936年にはメンバーの念願だった「日本民藝館」が東京・駒場に完成して、柳が初代館長に就任。この「美術館」と「出版」「流通」の三本柱を掲げ、地方の人・モノ・情報までをつないで協働した民藝のネットワークが育まれていった。
このネットワークは展覧会の第四章にある「民藝樹」の図に見てとれるが、まさにこれら民藝のモダンな「編集」の手法とローカルなネットワークこそが、民藝運動の特徴といえるだろう。
民藝を通じたディスカバー・ジャパン
当初、江戸時代を中心にした古い蒐集品が多かった民藝運動は、やがて日本の各地方で当時流通していた「現行品」を掘り起こし、その手仕事の保存や育成、産業化という目標へと活動を展開した。

その代表的な活動が、東北の民藝品調査と制作指導だった。柳宗悦たちは、蓑(みの)や藁沓(わらぐつ)など東北の農村で自給自足できる素材を使った雪国の手仕事とその美しさを評価。東京で東北民藝品展覧会を開催し、上位入選したものをたくみ工藝店が買い取るなど、その振興にも携わった。

これは沖縄で使われる「垢取り」と呼ばれる道具で、舟に溜まった水をくみ出すものだという。舟底の形に合わせた丸みを帯びた形がなんとも独特で、これもその土地ならではの知恵と工夫が生みだした民藝品の代表だ。
展覧会第5章には、こうした全国調査の成果を表現した全長13メートルを超える、芹沢銈介が制作した《日本民藝地図(現在之日本民藝)》(1941年、日本民藝館蔵)が展示されているが、民藝運動とはまさに日本の北から南までくまなく、隠れた手仕事の美と技を発見するムーブメントだった。各地の多様な民藝をひとつの日本に束ねる民藝運動の実践は、日本文化を代表するような存在へと高まっていくことになる。
戦後、日本が国際社会に復帰するなかで、民藝は<MINGEI>として国際交流の最前線に立つことになる。展覧会の第6章は、民藝運動の新たな可能性のひとつとして柳宗悦と濱田庄司が注目したモダン・デザインとの関係や、海外のデザイン界との交流。さらに民藝からインダストリアル・デザインへの展開が語られている。

写真は、柳宗悦の長男であるインダストリアル・デザイナーの柳宗理が原型をデザインし、1958年に京都五条坂の河井寬次郞の窯で焼かれた黒土瓶。民窯とのコラボレーションは、手と機械、工芸品と工業製品をつなぐ試みともいえる。
そして民藝運動は、日本のライフスタイルの変化に合わせて衣食住をトータルに提案していくような動き、さらに民家の保存、景観の保存といった領域にまでおよんだ。
いま私たちが「民藝」を知る場所としては、柳宗悦が初代館長を務めた東京・駒場の日本民藝館が有名で、本展の展示品の多くもそのコレクションからやってきている。柳宗悦は、美の本質に迫るためには、思想や嗜好、慣習といった先入観なく「直下に(じかに)」物を観ることが大切であると語り、日本民藝館でも作品の説明はあえておかれていない。その点、この「民藝の100年」では、450点を超える作品や資料を豊富な情報とともに展示していて、その全体像や背景が丁寧に紹介されている。民藝をまだよく知らない人にも、もっと知りたい人にも、きっと学ぶことの多い機会になるはずだ。
柳宗悦没後60年記念展
「民藝の100年」
会期:開催中〜2022年2月13日(日)まで ※会期中一部展示替えあり
会場:東京国立近代美術館(東京都千代田区北の丸公園3-1)
開館時間:10:00〜17:00(金・土曜日は20:00まで)
※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜日(ただし1月10日は開館)、年末年始(12月28日(火)〜1月1日(土・祝))、1月11日(火)
料金など詳しくは展覧会公式サイト:https://mingei100.jp
※開館時間などの最新情報は展覧会公式サイト等で事前にご確認ください。
文・杉浦岳史

















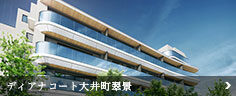

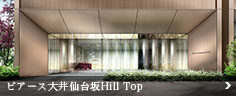






-7.png)
-4.png)

