みなさんこんにちは!弁護士の菅原草子です。以前の連載からあっという間に時間が過ぎ、2025年も残すところ3か月、もはや今年もありがとうございましたの勢いです。日々全力!を掲げた今年ですが、予想外の激動で、丁寧さに欠けてしまったのではと少し反省。残る3か月を1年分の丁寧さで上書き保存したい!
激動の要因の一つ、今年はインハウスローヤーとして企業でも働いていました。企業の一員となって感じるのは、制度が充実しているということ。個人事業主という一匹狼的働き方との違いを体感しています。休暇や手当てなど、会社ってすごい。
そんな会社にも大きく関係する「育児介護休業法」。昨年の改正が、いよいよ今年2025年4月1日と10月1日から施行されました。
何が変わったの?私たちの生活にどんな良いことがあるの?今回はそんなポイントをまとめてみたいと思います。
1 育児介護休業法とは
育児介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)は、労働者が、育児・介護と仕事とを両立できるような支援をすることを目的として、育児休業・介護休業に関する制度や事業主がとるべき支援措置等を定める法律です。少子高齢化が進み、労働人口が減少しているなかで、育児・介護により離職者が増えることで、更に労働者が減少してしまうことを抑止するねらいがあります。
2 どんな制度やルールが定められているの?
育児介護休業法は、主に以下のような制度を定めています。
<育児関連>
① 育児休業
子育て中の労働者が、原則子どもが1歳になるまで取得できる休業制度です。一定条件を満たせば、雇用保険から「出生時育児休業給付金」として、休業開始時の賃金の67%が支給されます。
労働者は男女いずれでも問いませんが、女性の育休取得率は近年80%台で推移しているところ、男性の取得率は増加しているとはいえ30%ほどに留まっているとされます。
② 出生時育児休業(産後パパ休業)
子どもが生まれてから8週間以内に、4週間の休業を取得できる制度です。通常の育休とあわせて取得可能です。給付金は通常の育休と同様です。
③ 子の看護休暇
子どもの病気やケガをした際の看護や、通院・健康診断の付き添いなどのために取得できる休暇です。未就学の子どもを養育する労働者を対象に、子ども1人につき年5日間付与されます。
④ 短時間勤務制度
3歳未満の子どもがいる労働者を対象に、一日の勤務時間を原則5時間45分〜6時間に短縮できる制度です。
⑤ 労働時間の制限
3歳未満も子どもがいる労働者について残業を免除する制度や、小学校入学前の子供がいる労働者について、深夜業を免除する制度などがあります。
<介護関連>
① 介護休業
労働者が、負傷や疾病、背引退精神上の障害により2週間以上の期間にわたり介護を必要する状態(要介護状態)にある家族がいる場合に、介護やお世話のために取得できる休業です。通算93日まで3回にわけて取得可能で、一定条件を満たせば、雇用保険から「介護休業給付金」として休業開始時における月額賃金の67%が支給されます。
② 介護休暇
介護休業同様に、家族の介護やお世話のために1年において5日まで取得できるお休みです。当日の申告でも、時間単位の取得でも可能です。
③ 短時間勤務等制度
要介護状態の家族を介護する労働者を対象に、介護が終了するまで、一日のまたは週や月の勤務時間、所定労働日数を短縮できる制度です
④ 労働時間の制限
要介護状態の家族を介護する労働者を対象に、介護が終了するまで、残業や深夜業を制限することができる制度です。
3 今回の改正のポイントは?
大きな方針としては、
1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2)育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
とまとめられますが、具体的には以下のような制度や義務が定められました。施行日ごとにまとめてみます。
~2025年4月1日施行~
①子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲が小学校3年生修了まで拡大され、子の入学式等の行事参加等の場合も取得事由に追加されました。また、勤続6月未満の労働者を除外する規定が廃止されました。
②所定外労働の制限対象の拡大
対象となる労働者の範囲が、3歳に満たない子を育てる労働者から、小学校就学前の子を育てる労働者に拡大されます。
③育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を育てる労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークが追加され、労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主には努力義務化されます。
④育児休業取得状況の公表義務が拡大
従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられていた育児休業等の取得状況の公表が、従業員数300人超の企業に義務付けられます。
⑤介護休暇取得の要件緩和
取得可能な労働者の要件について、勤続6月未満の労働者を除外する規定が廃止されました。
⑥介護離職防止のための措置
事業者は、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度等に関する制度等の周知と利用の意向の確認を個別に行わなければならず、また介護両立支援制度を取得しやすいよう、研修の実施や相談窓口設置等の措置を講じることも必要となります。
~2025年10月1日施行~
⑦育児期の柔軟な働き方を実現すための措置と個別周知・意向確認の義務化
3歳以上小学生就学前の子を育てる労働者に対して、柔軟な働き方を実現するため、事業主は、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して設置する必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等
- 保育施設の設定運営等
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与
また、事業主は選択した措置について、労働者に周知し、制度利用の意向について確認をする必要があります。
⑧個別の意向確認の義務化
事業主は、労働者が妊娠・出産を申し出た時や子どもが3歳になる前に、
- 勤務時間帯
- 勤務地
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件等)
について、面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかによって、意向を聴取しなければならず、その以降について配慮する必要があります。
以上を主な内容として、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境を整えるために、重要な変更のあった今回の改正。これを機会に、自分が対象となる制度がないか、より良い労働環境にすることができないか、確認してみると良いのではないでしょうか。万が一勤務先の就業規則に十分に定められていなかった場合でも、法を根拠に取得、利用できる制度もあります。また、事業主としては、必要な制度の整備や支援を実施しなければなりません。育児介護休業法に違反した場合には、行政指導や勧告があり、勧告に従わない場合には企業名の公表や、報告が求められた場合に虚偽の報告を行うと20万円の過料が科せられるなど、罰則もあるため十分に注意すべきです。
今回の改正により、労働者がやりたい仕事から離れず意欲的に働くことができるようになること、企業としても長期的な人材の確保に繋がることを期待して、労働者も企業も適切かつ有効に制度を活用していきたいですね。
【参照】
・厚生労働省 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

弁護士 菅原草子(スガワラソウコ)
仙台市出身。都内法律事務所所属。個人から企業まで分野を問わず相談をうける、駆け込み寺的存在を目指している。
大学院農学研究科で食品成分の研究をしていた異色の経歴をもち、企業の社外役員も務める。
趣味は、ビールと美味しいごはんと海外旅行。
instagram:@sooco_s328















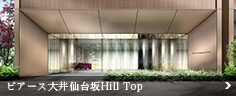






-7.png)
-4.png)

