トルコの都市イスタンブールといえば、あなたはどんな風景を思い浮かべるだろう。眩しい海と太陽、イスラム文化の美しい模様があふれるモスク、そして世界に名だたる食文化と香辛料の色彩・・・。ヨーロッパとアジア、ふたつの大陸にまたがる世界で唯一無二の大都市は「文明の交差点」などと呼ばれている。ここでは、宗教も、美術も、建築も、ひとつの様式にとどまることなく、歴代の征服者たちの文明を映し、つねに重なり合いながら現代にまでつながってきた。

今回の「アートをめぐる旅」は、このイスタンブールを舞台に、前編と後編の2回にわたって、二千年を超える歴史が積み重なる文明の層を探っていきたい。





ヨーロッパとアジア、ふたつの文明を包容するしなやかさ。
イスタンブールは、猫の街だ。歩道の真ん中、カフェの椅子の上、トラムの停留所のベンチ、ショーウィンドウの中、どこにでも猫がいて、人々は追い払うどころか、まるで隣人や同じ市民のように受け入れ、大切にしている。この街にいて感じるのは、猫が暮らしに溶け込んでいるように、人々が“共に生きる”ことをあたりまえのように受け入れる包容力だ。そのしなやかさは、もしかして文明の交差点を生きてきた民族の知恵やDNAのようなものなのかもしれない。

この地は、古代ギリシャがビザンティオンという植民都市を造ったことから、街としての歴史が始まったとされる。後にローマ帝国がここを支配下にすると、皇帝コンスタンティヌス1世は自分の名を刻んだ街「コンスタンティノープル」を築く。ローマ帝国が東西に分裂したあと、西ローマ帝国はゲルマン民族の大移動で滅亡してしまったが、コンスタンティノープルを首都にした東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は存続し、キリスト教国の盟主としてヨーロッパに君臨することになる。

その頃にキリスト教の大聖堂として誕生したのが「アヤ・ソフィア」だ。西暦537年、ユスティニアヌス1世によって建造されたこの巨大な聖堂は、完成当時「この世に類のない規模」と記されたという。幾度も崩壊と再建を繰り返しながら、重力にあらがうような大きなドームが造られていく。巨大な内陣を満たす光は、当時の人々にとってまるで天からの啓示のように見えたことだろう。


この大聖堂の時代に描かれたのが、金色に輝く美しいモザイク画だ。極小タイルの集合体とこの人物の描き方は、いわゆる「イコン画」の形式的なスタイルで、のちにビザンティン様式とも呼ばれるようになる。西ヨーロッパでは、中世からルネサンスへと移るにつれて教会の絵画のスタイルが変わっていき、形式的なイコン画はすたれ、写実や遠近法が重視されたフレスコ画や油絵が主流になった。しかしギリシャや東欧のいわゆる「正教会」の各地には、まるで中世から時が止まったかのように、今も当時に近いスタイルの美術が教会に残されている。現代のフランスやイタリアの教会美術と比べても、その違いがとても興味深い。

時代が一変、キリスト教の大聖堂が、イスラム教のモスクになる。
ところがコンスタンティノープルの東方で強大な力を持ったイスラム教国のオスマン帝国が、ヨーロッパ方面に進出。1453年には数百年つづいた東ローマ帝国を倒して、このコンスタンティノープルを手に入れた。歴史で言う「コンスタンティノープルの陥落」だ。
異教の象徴となったアヤ・ソフィアは、オスマン帝国のスルタン(皇帝)メフメト2世の手で、イスラム教の礼拝堂である「モスク」に変わることに。キリスト教のモザイクの上には漆喰の壁が塗られ、建物の横には、モスクの象徴である「ミナレット」と呼ばれる尖塔のようなシンボルが立てられた。
それでもオスマン帝国は、キリスト教徒を改宗したり、街から全面追放することはなかったという。イスラム教が主役の国にあっても、キリスト教の礼拝は認められ、人々は“共に生きる”ことを選んだのだった。

そしてふたたびモザイク画がよみがえる。
400年以上にわたるコンスタンティノープル支配のあと、オスマン帝国が滅亡したのは1922年。「トルコ共和国」として、イスラム教国でもキリスト教国でもない国家が誕生し、コンスタンティノープルは「イスタンブール」と呼ばれるようになる。モスクでなくなったアヤソフィアは、博物館として公開されると同時に修復が始まり、漆喰で隠されていた壁の下から、もうすっかり忘れ去られていた美しいモザイク画が現れたのだった。


モザイク画は、ご覧の通り、主にガラスでできたごく小さなタイルの集合で画面が構成されている。金色の背景は、権力を示すためではなく、永遠性を表現する「天上の光」の象徴であると考えられていた。窓から入る光やろうそくの炎に照らされて輝き、揺らめくモザイクの表情には、平面の絵にはない神秘性が生まれ、見る人を祈りの世界へといざなう。さらに青いガラスは聖性や宇宙を表現するものとしてモザイク画の美しさを引き立たせ、今これを見る私たちをも敬虔な気持ちにさせる。
時代は移っても、共存する文化と芸術。
礼拝堂として使うことが禁じられてきたこのアヤ・ソフィアは、2020年7月、エルドアン大統領のもとで、再び「モスク」として使われることになり、世界に波紋を起こした。今ではイスラムの教義を表すカリグラフィー(文字による装飾)が堂内に掲示され、礼拝の時にはキリスト教を象徴する偶像は幕で覆われる。それでもなお、モザイクは残され、その美しい姿を観客である私たちに見せる。


キリスト教文化とイスラム文化が共存し、歴史と文明の積み重なりを受け継ぎながら現代を生きる建築、アヤ・ソフィア。これからも、調和と対立を繰り返しながら人類がたどってきた軌跡を、長くとどめていてほしいと願うばかりだ。
アヤ・ソフィアを出ると、向かいにもう一つの巨大なドームが見える。ブルーモスク(スルタン・アフメト・モスク)だ。アヤ・ソフィアが歴史の層を象徴する建築だとすれば、ブルーモスクはオスマン帝国によるイスラム教の成熟した美意識を体現する建築といえる。次回は、このブルーモスクと、帝国の栄華を映したトプカプ宮殿の魅力をたどっていく。

(文・写真 杉浦岳史)













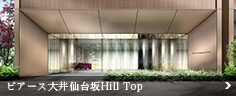






-7.png)
-4.png)

