旅に出ることは、つねに新しい世界への扉をひらくこと。見たことのない風景に出会ったり、見知らぬ文化、違った価値観や視点にふれることで、自分の心が豊かになっていく。そこにアートとの出会いが加わると、さらに私たちの五感は研ぎ澄まされて、旅は発見や感動に満ちた体験となるはずだ。
「SUMAU」がお届けする新シリーズ「アートをめぐる旅」の第一回は、フランス・パリが舞台。観光客でにぎわうシャンゼリゼ大通りを歩きながら、まずフランスにおけるアートの殿堂のひとつ「Grand Palais グラン・パレ」へと行ってみよう。

「グラン・パレ」は日本語に訳すなら「偉大な宮殿」という意味だが、ここが王や貴族の宮殿だったことはない。最初は1900年に開催されたパリ万国博覧会のパビリオンとして、隣接するプティ・パレやすぐ横を流れるセーヌ川にかかるアレクサンドル3世橋とあわせて建設され、世界中から訪れる観客を迎えたという。今でも3つの建築は往時の姿を留めていて、こうした歴史を感じながら歩いているだけでも楽しい。



「グラン・パレ」は、まるで大きな植物園のように、ガラスと鉄で覆われた「ネフ(身廊)」と呼ばれる中央部の大空間をシンボルに、数々の展覧会が開催されるギャラリーなどからなる壮大な建築。ここは2021年から2024年まで大規模な改修が行われ、パリ五輪に合わせて徐々に再オープン。フェンシングやテコンドーなどの試合が開催されたことは記憶に新しい。


新しくなったグラン・パレは、より多くの人々の日常に近い「暮らしの場」として利用されることをそのコンセプトにしているという。近年この施設は、展覧会のほかにもファッションショーや国際的なアートフェアなど、特別なイベントに使われることが多い。改修後の今はそれに加えて、ブティックや書店、レストラン、子どもたちの自由な遊び場など無料開放スペースを用意。まさに街を散策する気軽さで立ち寄れる、開かれたスポットへと変化しつつある。

その一環として、この夏にネフで無料開放されたのは、ブラジルの現代美術家で世界的に知られたエルネスト・ネトによるインスタレーションの展示だ。彼は、主に伸び縮みのある薄い布地に、香辛料や木材などの素材を使った生命体のような造形で、鑑賞者の視覚や触覚、嗅覚を揺り動かす作品を創出する。今回もこの開放的な空間に、まるで新たな生命体が出現したかのような風景を生みだした。

インスタレーションの中には、世界中から集められた太鼓などの楽器が作品と一体になっておかれている。観客が作品の中に足を踏み込んで、触感や匂いを感じながら楽器を演奏できるインタラクティブなイベントも行われた。
このネフの地上から大階段を上がった先にある空中の回廊では、同じくブラジル出身の気鋭の画家たちによる作品が展示された。非日常的なグラン・パレの大空間で、まさに散策するように回遊しながら、壮大なアート作品に包まれる贅沢が味わえる。


今後も、主にギャラリーで開催される有料の美術展のほかに、こうした自由に開かれたイベントを企画していく予定というグラン・パレ。旅行の際にはぜひウェブサイトで情報をチェックしておきたいスポットだ。
さて今度は、パリ8区から16区へと場所を移して、パリ市立近代美術館界隈を歩いてみよう。こちらもセーヌ川に沿ったエリアで、この美術館を含むパレ・ド・トーキョーという建物は、1937年に開催されたパリ万博にやはりパビリオンとして建てられた。このあたりからはエッフェル塔が間近に見える絶好のビューポイントでもある。



今、このパリ市立近代美術館では、日本でも人気がある20世紀モダンアートの巨匠アンリ・マティス(1869〜1954)の展覧会「マティスとマルグリット 〜 父の眼差し」が開催されている。マルグリットとはマティスの実の娘の名で、巨匠の生涯を通じてもっとも長く、数十年にもわたって描かれたモデルだった。時代につれて絵画のスタイルを大きく変えていったマティスだったが、娘に抱いていた愛情は変わることなく深く、どこか彼女の姿に自分自身を映す鏡のようなものを見ていたと言われることもある。

マルグリットは、マティスがまだ画学生だった頃に、そのモデルであったカロリーヌ・ジョブローとの関係から生まれた。彼女はその後、マティスとその妻アメリーとの間に生まれた義弟のジャン、ピエールとともに育つことになる。後年マルグリットは、この家族の絆を「私たちは手の五本の指のようなもの」と語っているという。

彼女は、幼い頃から虚弱体質で、7歳のときには気管切開手術を受ける。彼女を描いた絵がいつも首飾りをしていたり、首を隠していたりするのはそのためだ。同年代の子どもたちが学校に行っているあいだ、彼女は家にいなければならず、それがゆえに彼女は父のアトリエでつねに絵の鑑賞者となり、その足跡をたどっていく貴重な存在になっていった。


興味深いのは、ほかのモデルと違い、娘である彼女は父親に反抗し、批判し、時には作品についてさえ意見を申し立てることができたことだという。強い個性を持つ父と娘だけに、紆余曲折もあったというが、それだけに、ほかにはないマティスの裏側の姿が見える気がする。よく知られている巨匠の、あまり知られていない娘マルグリットとの関係を通じて、マティスの違った一面や物語を垣間見る貴重な機会になることだろう。

あなたがマティス・ファンなら、このパリ市立近代美術館に常設展示されている「La Danse(ダンス)」を逃さず見ておきたい。

これは、アメリカの著名な美術コレクターであるアルバート・バーンズが、現在のバーンズ財団美術館に設置するためにマティスに依頼したもの。マティスはこの注文のために数々のデッサンを描き、満を持して本番に臨んだのだが、制作途中でサイズが設置する場所と違っていたことが判明した。結局、新たに制作しなおすこととなり、このサイズ違いのバージョンがパリに残され、マティスが別の作品として仕上げたという、いわくつきの作品だ。
マティス自身が「戦闘的」と評したこちらのバージョンは、流麗かつ力強い線で、上へ下へとダンサーたちが躍動するダイナミックな表現が特徴。同じ展示室におかれた原寸大の習作と比べても、その違いは明らかだ。彼が追いかけた「ダンス」というモチーフにかけた試行錯誤を探ってみても面白いだろう。

パリ市立近代美術館を後にしたら、ぜひ目の前にあるパリ市立モード美術館(ガリエラ宮)の前庭を活かした公園「ガリエラ宮広場」のベンチへ。ルーヴル美術館やシャンゼリゼ通りの喧噪から遠く離れてひと休み。しばしパリ16区の市民になったつもりで、美しい建築と広がる空、丁寧に手入れされた花や緑を眺め、ゆっくりと深呼吸してみるのも、パリの旅の醍醐味といえそうだ。

Grand Palais グラン・パレ
所在地:Square Jean Perrin – 17 Avenue du Général Eisenhower 75008 Paris(展示スペースにより入口は異なります)
公式ウェブサイト:https://www.grandpalais.fr/en(英語)
Musée d’Art Moderne de Paris パリ市立近代美術館
所在地:11 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
「マティスとマルグリット 〜 父の眼差し」展は2025年8月24日まで
公式ウェブサイト:https://www.mam.paris.fr/en(英語)
(文・写真)杉浦岳史













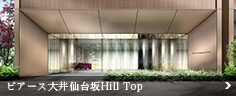






-7.png)
-4.png)

