お菓子などによく使う「ホイップクリーム」が、フランスでは「シャンティイ」と呼ばれていることを知っているだろうか。
その名が生まれたのは、フランスブルボン王朝全盛期の太陽王・ルイ14世の頃。パリの北にある「シャンティイ」のお城で給仕長をしていたヴァテルが、ルイ14世のためにクリームに砂糖を入れて泡立てる新しいお菓子を考案した。それは瞬く間に広がり、やがて「クレーム・シャンティイ」と名づけられたという。
壮大な森が広がる中のお城の町。今回はこの「シャンティイ」が舞台だ。

パリから急行で約25分ほど。ピカルディ地方の入口にあたるこの町にあるシャンティイ城は、フランスに数多く残る貴族のお城の中でもパリから電車で訪れることのできる数少ない場所のひとつ。知名度でいえば、かつて王様がいたヴェルサイユ宮殿やフォンテーヌブロー城にはかなわないが、実はここはルーブル美術館級ともいえる絵画の名作がならぶ世界的にも貴重なアートスポットなのだ。

静かな駅を降りると、すぐに森の遊歩道があらわれ、訪れる人をいざなう。この町は19世紀にさかのぼるシャンティイ競馬場でも知られるが、途中そのレースコースを見ながら歩を進めていくと、20分ほどで美しく水に浮かぶシャンティイ城が見えてくる。

まさに童話にも出てくるような「お城」の風景。14世紀に城の礎が造られ、16世紀にはルネサンス時代の名君でレオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに迎えたことでも知られるフランソワ1世の軍人でもあった「大元帥」アンヌ・ド・モンモランシー公に受け継がれ、城が形づくられていく。
その後、王家であるブルボン家とも深いつながりのあるコンデ家がモンモランシー家と姻戚関係となってこの城を所有。王家との関係から、フランス革命時には城は大部分が破壊され、牢獄として使われたりもした。

それを再建し、シャンティイ城をいまの姿にしたのは、オマール公アンリ・ドルレアン。ナポレオン1世失脚のあとの王政復古でフランス最後の王になったルイ=フィリップの5番目の息子だった。
彼は自分の名付け親であり最後のコンデ公だったアンリの遺産を相続し、シャンティイ城の再建に乗り出す。ところが1848年の2月革命、ナポレオン3世の第二帝政と貴族にとって不遇な時代が続き、イギリスへの亡命を余儀なくされてしまった。しかしこの亡命生活のあいだに、彼はイギリスに渡っていたフランスの美術品や装飾写本などを収集。ヨーロッパを巡ってコレクションと研究も進め、1871年にフランスに戻るとシャンティイ城の再建を本格化し、1886年に城が完成すると、「コンデ美術館」として一般公開することを条件に、フランス学士院という国の機関に遺贈した。

面白いのは、彼の遺言書に書かれたその作品保存の方法だ。
それは「美術館のコレクションを外部に貸さないこと」そして「作品の展示方法を変えないこと」。実際に遺言は守られていて、そのおかげで展示室はすべて19世紀の美術館のスタイルが現代まで貫かれることになった。

かつてはルーブル美術館でも、絵画は壁に上下に2段3段と重ねて架けられていた。ここシャンティイ城のコンデ美術館は、その当時のまま壁が絵で埋められ、時代や学派に関係なく絵の大きさや領主のセンスで並べられているのが興味深い。

特に圧巻なのがこの部屋、その名も「絵画のギャラリー」。向かって左側にはカラッチなどのイタリア絵画、右側にはドラクロワやプッサンをはじめとしたフランス絵画の名作が展示されている。天窓からは柔らかい光が差し込み、奥にはまるでローマの聖堂のような円形建物のテラス。そこには、イタリア・ルネサンスの巨匠ラファエロの作品「ロレッタの聖母」やピエロ・デ・コシモの「美しきシモネッタ・ヴェスプッチの肖像」がさりげなく飾ってある。一貴族のプライベートなコレクションだったとは思えないほどの贅沢さだ。


さらに「楼台」と呼ばれる部屋には、19世紀フランスの新古典派の画家ドミニク・アングルの「自画像」や「ドヴォーセ夫人」、その他にもフランドル派のハンス・メムリンク、そしてここにもドラクロワの作品が並ぶ。美術の教科書を見るような質の高いコレクションと数で、近代絵画に関してはルーブルに次ぐフランス第2の美術館と呼ばれるのもうなづける。

一般的な美術館とは違うここシャンティイ城の特色が「図書室」だ。

シャンティイ城の最後の領主だったオマール公は愛書家でもあって、ここには彼が所蔵し、集めた約3万冊もの書物がある。中でもここの特色は、『ベリー公のいとも華麗なる時祷書』に代表されるような、中世のカトリック教会で信仰や礼拝の手引き書として作られた彩色装飾の美しい書物。そして印刷技術が発明された直後にできた15世紀末頃の活字本のコレクション。本の歴史がつまった風景を見ていると、それだけでワクワクしてくる。

城の見学を終えたら、ベルサイユ宮殿の庭園技師でもあったル・ノートルが設計・造園したフランス式庭園、そしてこの町の馬の文化を象徴する「大厩舎」も見ておきたい。

ちょっとした城のような大厩舎は、若き国王ルイ15世の摂政を務めたブルボン公ルイ・アンリのために造られた。王室や貴族は伝統的に馬との関わりが深いが、このルイ・アンリは心から馬を愛していて「人間が死ぬと馬に生まれ変わる」と信じていたという。そんな彼のために造られた特大の厩舎は、馬博物館となって今に残る。本物の馬たちもいて、季節によって訓練のデモンストレーションやフランスの文化の一つである騎馬スペクタクルを見ることができる。

ほかにシャンティイには繊細なレース編みの伝統もあるのだが、訪れてみて印象的なのは、小さい町ながら凝縮したフランスの文化が詰まっていることだろう。それには、革命後の激動に翻弄されながらもその誇りを忘れなかったある貴族の努力があった。

実はフランス革命は、市民による新しい国づくりであると同時に、それまでの伝統をともかく壊すという荒波でもあった。王族や貴族の文化、そして教会などの文化遺産はこれによって深く傷ついた。そんななか、ここシャンティイ城をおさめたオマール公は、自身が国を追われる立場になりながらも、絵画や書物、工芸品などフランスが積み上げてきた文化を取り戻し、後世に残そうと奔走する。国を治める仕組みは変わっても、人間が創りあげた記憶の重要性に変わりはない・・・。そんな想いさえ感じられる名品のコレクション。ある意味、ヴェルサイユ宮殿よりも見ごたえがあるかもしれない。
シャンティイの町とシャンティイ城
パリ北駅から急行で約25分 Chantilly Gouvieux駅下車
シャンティイ城は駅から徒歩約25分
シャンティイ城入場料
(一般)城内、庭園、大厩舎の入場を含む 17€
(スペクタクルは別料金)https://www.domainedechantilly.com/
(文・写真)杉浦岳史
















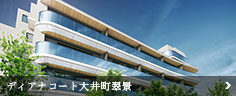

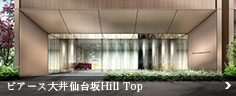






-7.png)
-4.png)

